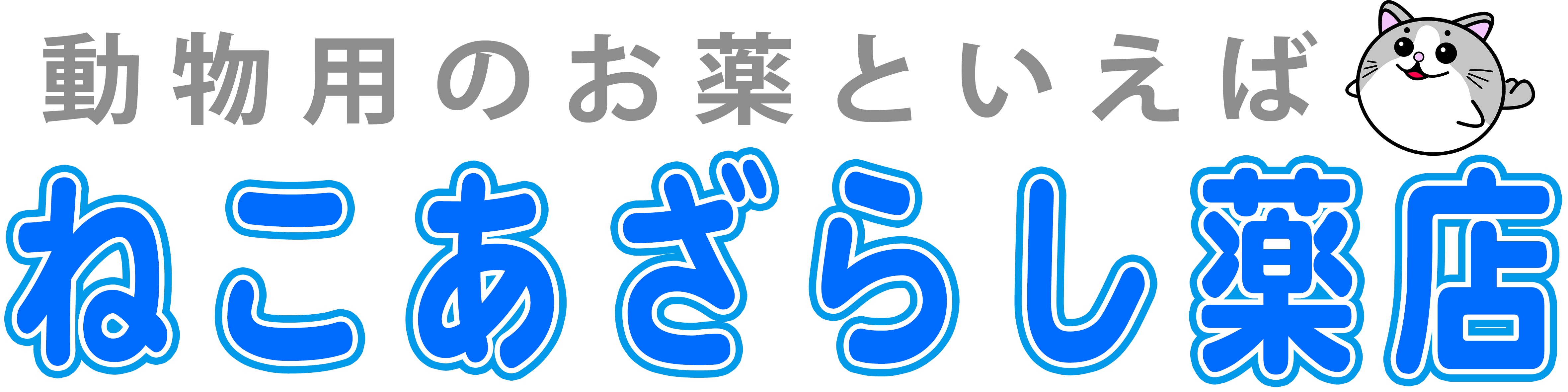療法食は、特定の健康状態に応じた栄養管理をサポートするために、栄養成分が調整された特別なペットフードです。
この記事では、犬猫の療法食について、主な種類や選び方、切り替え方法、食べない時の対策などを幅広く解説しています。
【この記事を読んでわかること】
- 療法食は特定の健康状態に応じて栄養成分が調整されたフード
- 腎臓サポート、尿路疾患サポート、消化器サポートなど目的別に種類がある
- 療法食への切り替えは基本的には段階的に行うことが重要
- 食べない場合はトッピングや温める、メーカーを変更するなどの対策が有効
- 療法食の使用は必ず獣医師の指導のもとで行う
最後まで記事を読んで、犬猫の療法食について学んでみましょう。
療法食の購入を検討中の方は、ぜひ動物のお薬の専門店「ねこあざらし薬店」にご相談ください。
療法食とは

療法食の定義
療法食とは、特定の健康状態や疾患に対応するために、栄養成分が調整された動物用のフードです。
通常のペットフードとは異なり、タンパク質やミネラル、脂質などの特定の栄養素の量が調整されており、獣医師の指導のもとで使用されます。
療法食の目的
療法食は以下のような目的で使用されます。
『栄養管理のサポート』
腎臓病や尿路結石、消化器疾患などの健康問題を抱える犬猫に対して、適切な栄養バランスを提供します。
例えば、腎臓病用の療法食では、リンやナトリウム、タンパク質の含有量が調整されており、腎臓への負担を軽減するように設計されています。
『健康維持の補助かつ疾患の治療』
療法食は栄養管理を通じて健康維持をサポートすると共に疾患の治療方法の1つとして使用することがほとんどです。
適切な栄養バランスを維持することで、疾患の原因を減らしたり、再発を防いだりなどの効果が期待されます。
『症状の進行管理』
特定の健康状態において、食事による栄養管理を行うことで、症状の進行に配慮した対応が可能になります。
獣医師の診断と指導に基づいて適切な療法食を選択することが、犬猫の長期的な健康管理に役立ちます。
療法食の主な種類

犬猫の療法食には、健康状態に応じてさまざまな種類があります。
腎臓サポート療法食
| 項目 | 内容 |
| 対象 | 慢性腎臓病の犬猫 |
| 特徴 | リン、ナトリウム、タンパク質の含有量を調整 |
| 目的 | 腎臓への負担を軽減し、健康管理をサポート |
腎臓サポート療法食は、慢性腎臓病の犬猫のために、特定の栄養素が調整されたフードです。
腎臓は主に体内の老廃物をろ過する重要な器官ですが、機能が低下するとその働きが十分に行われなくなります。
このフードは、リンやナトリウムの含有量を制限し、良質なタンパク質を適切な量で配合することで、腎臓への負担を軽減します。
また、水分含量が多めのウェットタイプも用意されており、適切な水分補給を促進する役割も果たします。
腎臓病は進行性の疾患であるため、早期からの栄養管理が重要です。
尿路疾患サポート療法食
| 項目 | 内容 |
| 対象 | 尿路結石、膀胱炎のある犬猫 |
| 特徴 | 尿のpHバランスを調整、ミネラル含有量を制限 |
| 目的 | 尿路の健康維持をサポート |
尿路疾患サポート療法食は、尿路結石や膀胱炎などの尿路トラブルを抱える犬猫のためのフードです。
尿のpHバランスを適切に保つことで、結石の形成リスクに配慮した栄養管理を行います。
また、マグネシウムやカルシウムなどのミネラル含有量が調整されており、結石の原因となる成分の過剰摂取を防ぎます。
さらに、犬猫が十分な水分を摂取できるように、ウェットタイプの製品が多く用意されています。
適切な食事選択と水分摂取により、尿路の健康を配慮した栄養管理が期待できます。
消化器サポート療法食
| 項目 | 内容 |
| 対象 | 下痢、嘔吐、消化不良のある犬猫 |
| 特徴 | 消化しやすい成分、食物繊維を配合 |
| 目的 | 消化器の健康維持をサポート |
消化器サポート療法食は、消化器系に問題を抱える犬猫のために設計されたフードです。
消化に優しい成分で構成されており、胃腸への負担を軽減します。
また、適切な食物繊維が配合されており、腸内環境を整える役割を果たします。
下痢や嘔吐、食欲不振などの症状がある場合、消化器サポート療法食を使用することで、消化器系の健康維持と栄養管理が期待できます。
肥満予防サポート療法食
| 項目 | 内容 |
| 対象 | 体重管理が必要な犬猫 |
| 特徴 | 低カロリー、高タンパク質、食物繊維を配合 |
| 目的 | 適切な体重管理をサポート |
肥満予防サポート療法食は、体重管理が必要な犬猫向けに開発されたフードです。
低カロリーでありながら、犬猫に必要な栄養素をバランスよく含んでおり、満腹感を得られる工夫がされています。
肥満は糖尿病や関節疾患、心臓病などさまざまな健康リスクを高めるため、適切な体重管理は犬猫の健康維持にとって重要です。
療法食を通じて、適切な体重管理をサポートすることが期待されます。
アレルギー対応療法食
| 項目 | 内容 |
| 対象 | 食物アレルギーのある犬猫 |
| 特徴 | アレルゲンとなる成分を除去または低減 |
| 目的 | アレルギー症状の管理をサポート |
アレルギー対応療法食は、特定の食物アレルギーを持つ犬猫のために開発されたフードです。
アレルギー反応が起きにくい原材料と成分が使用され、一般的に単一のタンパク源と炭水化物源で構成されています。
これにより、飼い主はアレルギーの原因を特定しやすくなります。
皮膚炎や消化器症状などのアレルギー症状がある場合、獣医師の診断のもとで適切な療法食を選択することが推奨されます。
療法食への切り替え方法

療法食への切り替えは、獣医師からすぐに切り替えるよう指示がない限り、基本的に1週間かけて段階的に行いましょう。
急激な食事の変更は、犬猫にストレスを与え、消化不良や食欲不振の原因となることがあります。
切り替えのステップ
療法食への切り替えは、一般的に以下のようなステップで行います。
| 日数 | 従来のフード | 療法食 |
| 1〜2日目 | 75% | 25% |
| 3〜4日目 | 50% | 50% |
| 5〜6日目 | 25% | 75% |
| 7日目以降 | 0% | 100% |
最初の数日は、従来のフードに療法食を少量混ぜて与え、徐々に療法食の割合を増やしていきます。
この方法により、犬猫が新しいフードに慣れることができ、消化器官への負担も軽減されます。
切り替え時の注意点
- 獣医師の指示に従って切り替えのペースを調整する
- 犬猫の様子を観察し、下痢や嘔吐などの異常があればすぐに獣医師に相談する
- 切り替え期間中は、他のフードやおやつを与えないようにする
- 十分な水分摂取を促す
療法食を食べない時の対策
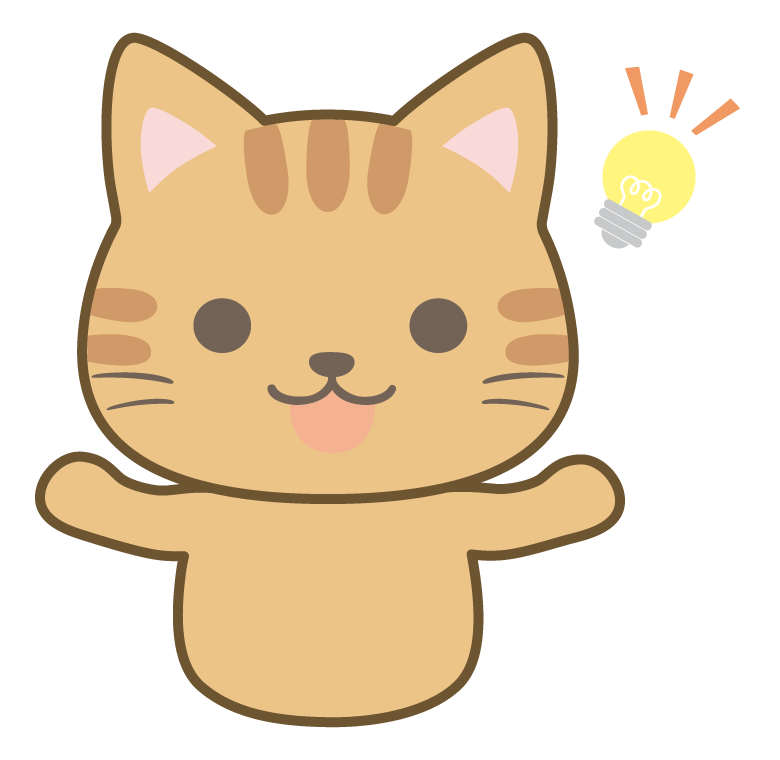
犬猫が療法食を食べてくれない場合、以下のような対策を試してみましょう。
対策①:トッピングの工夫
獣医師の指導のもと、疾患の治療に影響を与えないトッピングを加えることで、嗜好性を高めることができます。
例えば、以下のようなトッピングが効果的です。
- 鶏肉や魚のゆで汁
- 少量の鶏ささみ(茹でたもの)
- 犬猫用のスープ
ただし、トッピングの成分が療法食の目的に影響を与えないよう、必ず獣医師に相談してから使用しましょう。
対策②:フードを温める
ドライフードやウェットフードを少し温めることで、香りが引き出され、犬猫が食べやすくなることがあります。
電子レンジで10〜15秒程度温めるか、ぬるま湯をかけてふやかすなどの方法が有効です。
温めすぎると栄養素が損なわれる可能性があるため、人肌程度の温度を目安にしましょう。
対策③:食事環境の見直し
食事をする場所を静かで落ち着いた場所に移すことで、ストレスを軽減し、リラックスして食事を取ることができるかもしれません。
周囲の騒音や刺激を排除し、落ち着いた環境を提供することが大切です。
また、食器の種類や高さを変えることで、食べやすくなる場合もあります。
対策④:食事の時間と回数を調整
1日の給餌回数を増やし、1回あたりの量を減らすことで、食べやすくなることがあります。
また、決まった時間に食事を与えることで、食事のリズムが生まれ、犬猫が食事を期待するようになります。
対策⑤:獣医師に相談
上記の対策を試しても療法食を食べない場合は、必ず獣医師に相談しましょう。
獣医師は、メーカーが異なっても目的が同じ療法食や、他の栄養管理方法を提案してくれます。
また、食欲不振の背景に病気の進行や他の問題がある可能性もあるため、早めの相談が重要です。
療法食使用時の注意点
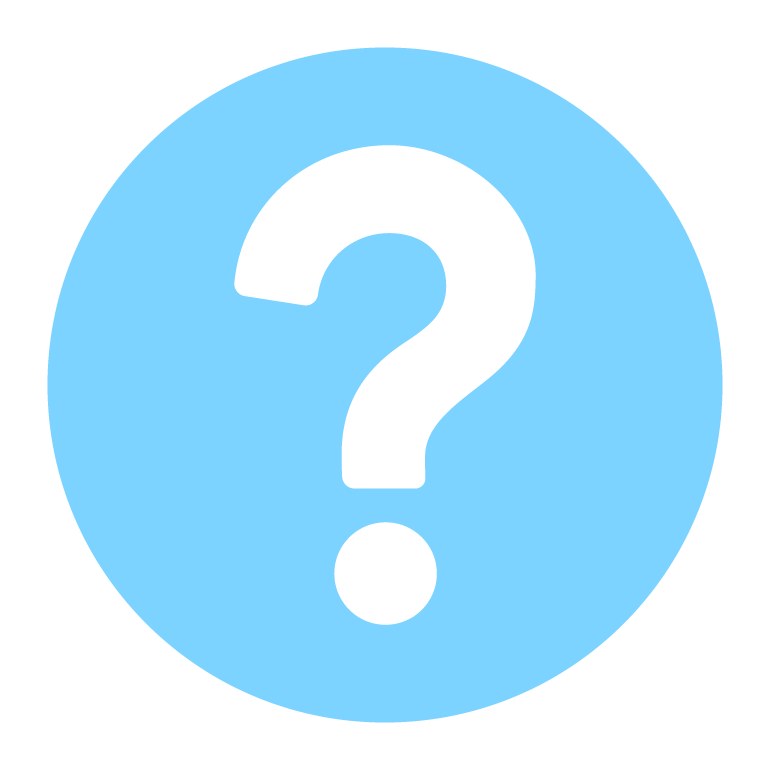
療法食を使用する際には、以下の点に注意しましょう。
注意点①:獣医師の指示に従う
療法食は必ず獣医師の指示に基づいて使用する必要があります。
自己判断での変更や中止は、犬猫の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
獣医師は、犬猫の健康状態に応じた最適な療法食を提案してくれます。
注意点②:他のフードやおやつの制限
療法食の効果を最大限に引き出すためには、他のフードやおやつを与えないことが重要です。
特定の成分に制限がある療法食の場合、他の食べ物を与えることで、その効果が損なわれる可能性があります。
どうしてもおやつを与えたい場合は、必ず獣医師に相談しましょう。
注意点③:適切な給餌量を守る
犬猫の体重や健康状態に応じて、適切な給餌量を守ることが大切です。
過剰な給餌は肥満を招き、不足は栄養不足の原因となります。
療法食のパッケージに記載されている給餌量を参考にし、獣医師と相談しながら調整しましょう。
注意点④:定期的な健康診断
療法食を使用している間は、定期的に動物病院で健康状態を確認することが重要です。
獣医師の診察を受けることで、療法食の効果をモニタリングし、必要に応じて種類や給餌量を調整することができます。
血液検査や尿検査などを定期的に行い、健康状態の変化を把握しましょう。
注意点⑤:水分摂取の促進
療法食を使用する際は、十分な水分摂取を促すことが大切です。
特に腎臓病や尿路疾患の場合、適切な水分摂取が健康管理に重要な役割を果たします。
新鮮な水を常に用意し、複数の場所に水飲み場を設置するなどの工夫をしましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1. 療法食だけで栄養は足りますか?
A. はい。療法食は総合栄養食として設計されており、療法食と水だけで必要な栄養を満たせます。
Q2. 複数の病気がある場合はどうしますか?
A. 獣医師が優先すべき疾患を判断し、最適な療法食を選択します。必ず相談しましょう。
Q3. 療法食はずっと続ける必要がありますか?
A. 疾患の種類や進行度によります。慢性腎臓病など継続が必要な場合と、一時的な使用で済む場合があります。
Q4. 療法食は高価ですが、本当に必要ですか?
A. 療法食による適切な栄養管理は、病気の進行に配慮し、長期的な医療費の軽減にもつながります。
まとめ
ここまで、犬猫の療法食について、主な種類や選び方、切り替え方法、食べない時の対策などを幅広く解説してきました。
この記事のまとめは、以下のとおりです。
- 療法食は特定の健康状態に応じて栄養成分が調整されたフード
- 腎臓サポート、尿路疾患サポート、消化器サポートなど目的別に種類がある
- 療法食への切り替えは段階的に行うことが重要
- 食べない場合はトッピングや温めるなどの工夫が有効
- 療法食の使用は必ず獣医師の指導のもとで行う
療法食は、犬猫の健康管理において重要な役割を果たすものであり、獣医師の指導のもとで適切に使用することが大切です。
愛犬・愛猫の健康状態に応じた療法食を選択し、栄養管理を通じて健康維持をサポートしましょう。
療法食に関して疑問や不安がある場合は、必ず獣医師に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
療法食の購入を検討中の方は、ぜひ動物のお薬の専門店「ねこあざらし薬店」にご相談ください。
ねこあざらし薬店では、決済完了から最短翌日にお薬をお受け取りいただけます。
また、療法食に関するお悩みは、24時間いつでもLINEから薬剤師へご相談いただけます。
ねこあざらし薬店で販売している療法食は、以下からご覧ください。

岐阜大学応用生物科学部獣医学課程を卒業後、獣医師として動物愛護団体付属動物病院やペットショップ付属動物病院にて主に一次診療業務、ペット保険会社での保険金査定業務などに従事。現在は製薬関係の業務に携わりつつ、ペットの健康相談業務、動物関係のライティングに加えてペット用品並びに犬猫の健康記事に関する監修経験多数。なおプライベートでは個人で保護猫活動並びに保護猫達の健康管理実施中。