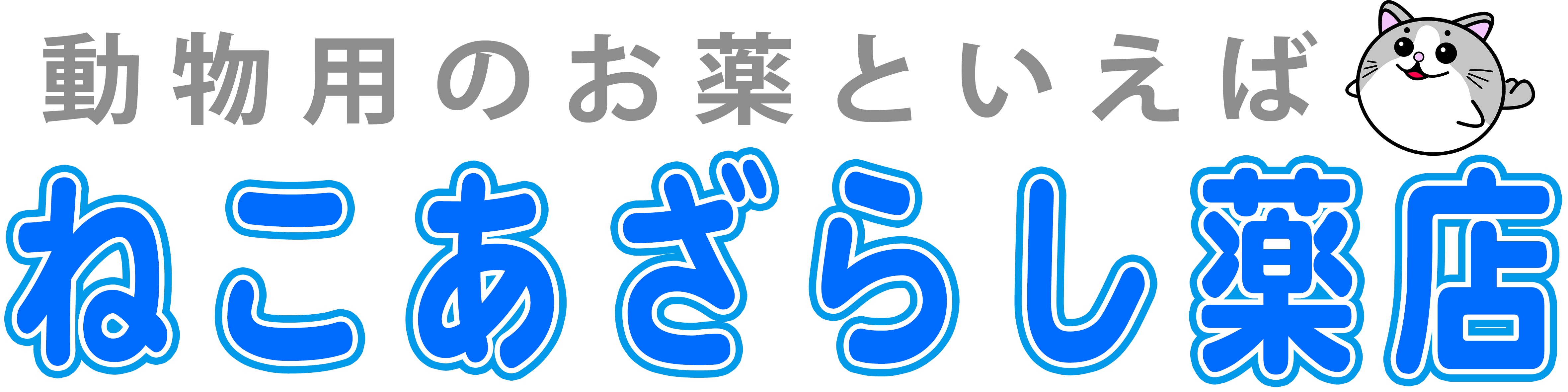目の症状
1. 原因と傾向
猫の目やにが出る主な原因は、眼の炎症や感染症です。
代表的なのは、ヘルペスウイルスやカリシウイルス、クラミジアによる上気道感染症です。これらの感染により結膜炎や角膜炎が生じ、炎症によって目やにが生成されます。特に生後2-3ヶ月の幼猫が感受性が高く、母猫からの抗体の減少に伴い発症しやすくなります。
アレルギーによる炎症でも目やにが見られます。花粉、ハウスダスト、食物、皮屑などのアレルギー源が眼に接触することで、アレルギー性結膜炎を発症し、目やにを引き起こします。アトピー性皮膚炎を有する猫では、アレルギー性結膜炎を併発することも少なくありません。
その他、砂やホコリなどの異物の機械的刺激、猫同士のけんかなどによる傷での炎症、眼瞼異常などでも目やにが生じます。
このように、目やにの原因にはウイルスや細菌による感染症、アレルギー、異物刺激、外傷など、様々なものがあります。
2. 発見方法と対策
まず結膜の充血や浮腫、目やにの量・性状・色調を確認します。
他の症状の有無も合わせてチェックし、鼻汁、くしゃみ、咳などの有無で原因を絞り込みます。
原因の特定には、培養検査により感染症の有無を確認したり、アレルゲンとの皮内反応検査でアレルギーを調べたりします。
原因に応じて、抗生物質やステロイドの点眼薬を処方したり、アレルギー対策を行ったり、眼瞼異常に対する手術療法を行ったりします。
以上のように、目やにの特徴を総合的に判断し、検査結果に基づいて適切な治療を選択することが重要です。
3. 考えられる病気
- 角膜炎
- 結膜炎
- 白内障
- 眼瞼内反症
- 猫風邪(猫の上部気道感染症:猫カリシウイルス、猫鼻気管炎(ヘルペス)ウイルス、クラミジア・フェリス)
- 鼻炎
- 気管支炎
目の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の涙が出る主な原因は、眼の炎症や感染症、涙排出経路の異常です。
代表的なのは、ヘルペスウイルスやカリシウイルス、クラミジアによる上気道感染症です。これらの感染により結膜炎や角膜炎が生じ、炎症によって涙分泌が増加します。特に生後2-3ヶ月の幼猫が感受性が高く、母猫からの抗体の減少に伴い発症しやすくなります。
アレルギーによる炎症でも涙量が増えます。主な原因アレルゲンとしてはハウスダスト、花粉、食物などがあり、アトピー性皮膚炎を有する猫ではアレルギー性結膜炎の併発も少なくありません。
また、涙小管や鼻涙管の炎症により涙の排出経路が閉塞すると、涙の溢れが生じ涙目となります。眼瞼異常でも涙量が増加しやすくなります。
このように、涙の増加は眼表面の炎症や感染、アレルギー、涙排出障害など、様々なメカニズムが関係しているため、総合的な判断が必要です。
2. 発見方法と対策
まず結膜の充血や浮腫とともに、涙量の増加の程度を詳細に確認します。
他の症状の有無も合わせてチェックし、鼻汁、くしゃみ、咳などの有無で原因を絞り込みます。
原因の特定には、培養検査により感染症の有無を確認したり、アレルゲンとの皮内反応検査でアレルギーを調べたりします。
原因に応じて、点眼薬の処方、感染症治療、涙小管洗浄、眼瞼形成手術など、個別の治療を行います。
以上のように、涙目の特徴を総合的に判断し、検査結果に基づいて適切な治療を選択することが重要です。
3. 考えられる病気
- 角膜炎
- 結膜炎
- 白内障
- 眼瞼内反症
- 網膜変性症(網膜変性性疾患)
- 流涙症
- 気管支炎
目の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の目が白く濁る代表的な原因は白内障です。白内障は水晶体が濁って光を散乱させ、視力低下をもたらす病気です。
白内障には先天性と後天性があります。先天性白内障は稀で、血縁交配されたペルシャやヒマラヤン種で報告例があります。後天性白内障の原因としては、外傷、糖尿病や腎臓病などの全身疾患、眼内炎などの眼疾患があります。外傷後の白内障は片眼に限局することが多く、盲目は避けられる場合があります。
両眼性の全盲は生活動作に支障を及ぼすため重大ですが、片眼のみの障害では行動変化はあまり顕著とはなりません。白内障以外にも、緑内障、眼内炎、網膜萎縮など他の眼疾患によっても、眼内構造の障害で濁りを生じることがあります。
したがって、目の濁りの原因を特定するためには、発症の経緯や他の症状を確認するとともに、眼科検査や血液検査等を行う必要があります。
2. 発見方法と対策
まず眼の奥が白く濁ったかどうかを確認します。両眼か片眼か、程度の違いも詳細にチェックします。
他の症状の有無や行動の変化も観察し、原因を探ります。視力低下以外にも、眼の炎症兆候がないかを確認します。
眼科検査では、白内障の程度だけでなく、緑内障、眼内炎など他の眼疾患も調べます。必要に応じて血液検査も行います。
原因に応じて、点眼薬投与、白内障手術、全身疾患の治療などを行い、視力の改善を図ります。
以上のように、目の濁りの特徴を総合的に判断し、検査結果に基づき適切な治療を選択することが重要です。
3. 考えられる病気
- 白内障
目の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の目が赤い症状には様々な原因が考えられますが、大きく分けて感染症と非感染性疾患の2つが主な原因となります。
感染症の場合、主にウイルスや細菌による結膜炎や角膜炎が目の赤みの原因となります。代表的なのがヘルペスウイルスやカリシウイルスによる上気道炎で、結膜や角膜に炎症が起こり、目が赤く腫れ上がる症状がみられます。また、クラミジアなどの細菌感染による結膜炎でも、目の充血と赤みが特徴的です。これらの感染症は、幼齢期の抵抗力が弱い子猫に多くみられます。
感染症による目の赤みは、鼻やのどの粘膜の炎症が目にまで及ぶことで起こります。例えば、ヘルペスウイルスは上気道の粘膜細胞に付着・増殖することで鼻炎や気管支炎を引き起こし、さらに眼の粘膜組織にもウイルスが伝播して結膜炎や角膜炎を発症させます。猫カリシウイルスでも同様の経路で目の感染が成立します。また、クラミジアなどの細菌も上気道から目に伝播する場合があります。このため、目の赤みに伴って、くしゃみ、鼻汁、呼吸困難などの症状が合併することが特徴です。
一方で非感染性の目の疾患では、アレルギー性結膜炎やドライアイ、眼瞼内反などが目の赤みの原因となります。アレルギー性結膜炎は、ハウスダストなどの環境アレルゲンや食物アレルゲンを原因として慢性的な炎症が起こり、目が赤くなります。ドライアイでは涙液の分泌量が減少することで目の潤いが失われ、目の疲れから赤みが生じます。また、眼瞼内反は瞼の裏側の組織が瞼輪内に向かって反転・増殖することで、目を開けるのが困難になり、目の奥の粘膜が炎症を起こして赤くなります。
このように、目が赤くなる原因は様々ですが、感染症か非感染性疾患か、発症のパターンから原因を推測することができます。飼い主は普段から猫の目の状態に気を配り、異常が見られた場合は早めに獣医師の診断を受けることが大切です。
2. 発見方法と対策
猫の目が赤くなった場合、まずは次のような症状の有無を確認することが発見のポイントとなります。
- 目やにや涙の分泌の増加
- 目のかゆみによるこすり過ぎ
- 光を避ける動き
- くしゃみや鼻汁などの上気道症状
これらの症状がある場合は感染症の可能性が高いため、獣医師の診察を受ける必要があります。一方、目の疲れを訴えるような症状がある場合はドライアイの可能性も考えられます。
次に、目の赤み以外の目の異常の有無を確認します。白内障のような水晶体の濁りや、緑内障では見られる瞳孔の開大、眼瞼内反では瞼と目球の間に組織のはみ出しがあるなど、他の目の疾患を示唆する徴候がないかを確認します。
対策としては、まず獣医師の診断により原因を特定し、治療を開始することが基本となります。治療には、抗生物質や抗ヒスタミン薬などの点眼が中心となるでしょう。
また、感染性の場合は周囲への感染防止も必要です。さらに、根本的な原因が特定できれば、その原因を取り除くことが大切です。例えば、アレルギー性の場合は原因となるアレルゲンを避けることが重要です。
点眼治療では、点眼の回数と量を守ることが効果的な治療のカギとなります。獣医師の指示通りに点眼することが大切です。また、点眼後に目薬が目から流れ落ちないよう、少し目を閉じておくなどの配慮も必要です。
飼育管理では、目の傷を防ぐために猫をストレスから守ることが重要です。他の猫とのトラブルを避ける、猫の行動範囲を制限するなどの対策が考えられます。安静に過ごせる環境づくりが目の早期回復の助けとなります。
3. 考えられる病気
- 結膜炎
- 白内障
- 緑内障
- 網膜変性症(網膜変性性疾患)
- 猫風邪(猫の上部気道感染症:猫カリシウイルス、猫鼻気管炎(ヘルペス)ウイルス、クラミジア・フェリス)
- 熱中症
目の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
鼻の症状
1. 原因と傾向
猫の「鼻水・くしゃみをする」症状の原因には主に2つのパターンがあります。
1つは、ウイルスや細菌による上気道感染症が原因の場合です。代表的なのがヘルペスウイルスや猫カリシウイルスによる猫風邪で、これらのウイルス感染によって鼻腔やのどの粘膜が炎症を起こし、鼻汁やくしゃみなどの症状が出ます。具体的には、これらのウイルスは上気道の粘膜細胞に感染・増殖することで局所的な炎症反応を引き起こし、血管を拡張させたり、細胞を傷害したりして、鼻汁の分泌を増加させたり、くしゃみ反射を誘発したりするのです。また、これらのウイルス感染に二次的に細菌が感染することで症状がさらに悪化することもあります。このパターンでは、発熱や食欲低下など全身症状を伴うこともあります。
もう1つのパターンは、アレルギー性鼻炎です。花粉やハウスダスト、食物などのアレルゲンを原因として鼻粘膜が慢性的に炎症を起こし、鼻汁やくしゃみなどの症状が続くことを特徴とします。アレルギー性鼻炎の背景には、IgE抗体の関与があり、アレルゲンとIgE抗体が結合することでマスト細胞からヒスタミンなどのケミカルメディエーターが放出され、血管拡張や分泌の亢進などにより鼻炎症状が引き起こされます。アレルギー性鼻炎では、通常全身症状はみられません。
このように、鼻汁やくしゃみの原因にはいくつかのパターンがありますが、他の症状の有無などからある程度原因を推測することができます。飼い主には、普段の飼育環境や症状の変化に注意を払うことが大切です。
2. 発見方法と対策
鼻汁やくしゃみがある場合、まず次の点から原因を推測します。
- 他の上気道感染症状(発熱、食欲低下など)があるか
- 慢性的な症状か、急性的な症状か
- アレルギー性炎症を示唆する他の症状があるか
これらの観察により、概ね感染症かアレルギー性かを判断できます。次に、他の病気を併発していないか確認する必要があります。例えば、鼻腔や副鼻腔に腫瘍がないか、歯周病などの口腔疾患がないかなどを確認します。
対策としては、獣医師の診断により原因を特定し、治療を開始することが基本です。ウイルスや細菌感染の場合は抗生物質などの投与、アレルギーの場合は対症療法と原因アレルゲンの除去が重要です。飼い主には、飼育環境の見直しや衛生管理が求められます。例えば、粉じんやダニを減らす掃除の徹底、カビやハウスダスト対策が考えられます。また、定期的なワクチン接種による感染症予防も大切な対策の1つです。
3. 考えられる病気
- クリプトコッカス症
- 鼻炎
- 副鼻腔炎
- 結膜炎
- 気管支炎
- 結膜炎
- 肺炎
- 猫風邪(猫の上部気道感染症:猫カリシウイルス、猫鼻気管炎(ヘルペス)ウイルス、クラミジア・フェリス)
鼻の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の「鼻血が出る」症状の主な原因は、鼻腔粘膜の損傷や血管の異常です。
鼻腔粘膜が損傷する代表的な原因は、外傷です。猫同士のけんかや物にぶつかる事故などにより、鼻腔内の粘膜が切れたり傷つくことで鼻血が出ることがあります。鼻腔の粘膜は血管が豊富で血流も多いため、外傷により粘膜が損なわれると容易に出血するのです。また、鼻腔内に異物が入ったり、鼻炎や副鼻腔炎などの鼻腔の疾患や炎症がある場合も、粘膜が荒れて出血しやすくなります。これらの疾患では、炎症により粘膜が浮腫み、血管が脆弱化することで、擦過などの軽微な刺激でも出血を引き起こします。
一方、鼻腔内の血管に異常がある場合も鼻血の原因となります。例えば、腫瘍による血管の破綻や異常血管の形成、血小板数の減少などが起こると、わずかな衝撃でも血管が破れて出血するようになります。鼻腔粘膜にできた腫瘍は新生血管を伴うことがあり、これらの異常血管はもろく破れやすいため、出血を引き起こします。また、高血圧症により血管がもろくなっていると出血しやすくなります。高血圧は血管壁にストレスを加え、血管を脆弱化させるためと考えられています。
このほかにも、過度の興奮やストレス、熱中症などによる血圧の上昇が鼻血の引き金となることもあります。これらは一過性の血圧上昇を来たし、鼻腔粘膜の血管を破裂させるためと考えられます。
2. 発見方法と対策
鼻血が出た場合、まず外傷の有無を確認します。外傷があれば、それが原因と考えられます。外傷がなければ、鼻腔内の病変や全身疾患の可能性を疑い、獣医師の診断が必要です。鼻腔内に腫瘍がないか、鼻腔疾患がないか、血液検査で凝固能異常がないかなどを調べます。
対処としては、タオルなどで鼻の圧迫止血を行います。出血が多い場合は、動物病院での治療が必要になります。止血剤の投与や出血箇所のカウテリゼーション、輸血などの処置が行われる場合があります。
原因を特定するために、鼻腔内の観察や血液検査などを行います。原因に応じて、感染症なら抗生物質の投与、腫瘍なら除去手術、凝固異常なら血小板補充、高血圧なら降圧剤の投与といった治療を行います。
予防には、外傷を防ぐこと、鼻腔の清潔保つこと、全身状態の管理などが重要です。鼻血を繰り返す場合は、原因究明と治療が必要不可欠です。早期発見・早期治療を心がけることで、重症化を防ぎましょう。
3. 考えられる病気
- 副鼻腔炎
- クリプトコッカス症
鼻の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
口の症状
1. 原因と傾向
猫の口臭の主な原因は、歯周病や口内炎などの口腔内の疾患です。歯周病では歯肉の炎症、口内炎では粘膜の炎症が原因となって強い口臭が生じます。
歯周病は歯垢に含まれる細菌の増殖によって発症し、歯肉の炎症から始まります。歯垢には多数の細菌が存在しており、その中には口臭の原因物質となる揮発性硫黄化合物を産生する細菌が含まれています。これらの細菌が歯肉の付着した部分で増殖することで歯肉炎を引き起こし、炎症が進むにつれて歯肉からの出血や歯のぐらつきが生じ、口臭が強くなります。
口内炎もウイルス感染などを原因として口腔粘膜が炎症を起こし、ただれや潰瘍、出血を伴うことがあり、これに伴い強い口臭が生じます。口内炎では、炎症によってタンパク質が分解されることでアンモニアなどの口臭成分が生成されると考えられています。
このほか、口臭の原因としては、胃食道逆流症や腎疾患による尿毒症、糖尿病などの全身疾患も関与していることがあります。これらの疾患では体内の老廃物が排出されず口臭の原因となる物質が蓄積するためと考えられます。
2. 発見方法と対策
口臭がある場合、まず歯周病や口内炎などの口腔疾患の有無を確認する必要があります。歯の手入れをしっかり行っているにも関わらず口臭が強い場合は、胃食道逆流症や腎疾患などの可能性も考えられ、獣医師の診断が重要です。検査では口腔内の観察に加えて、血液検査や腹部エコー検査などを行い、口臭の原因を特定します。
対策としては、原因疾患の治療が基本となります。歯周病では歯石除去と口腔清潔の維持、口内炎では原因ウイルスの治療、全身疾患では専門的な治療が必要です。
予防には日頃の口腔ケアと定期健診による疾患の早期発見が大切です。猫用の歯ブラシを用いたブラッシングや歯磨きシートの使用がおすすめです。適切な対応により口臭の改善が期待できます。
3. 考えられる病気
- 歯周病
- 口内炎
- 猫風邪(猫の上部気道感染症:猫カリシウイルス、猫鼻気管炎(ヘルペス)ウイルス、クラミジア・フェリス)
- 尿毒症
- 急性腎不全
- 水腎症
口の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の口の中の出血の主な原因は、歯周病や口内炎などの口腔内の疾患です。
歯周病では、歯肉の炎症と歯ぐきからの出血が特徴的です。歯垢に含まれる細菌が増殖して歯肉に炎症を起こし、歯肉が赤く腫れて出血しやすくなります。歯肉の炎症が進むと歯肉は徐々に退縮し、歯との間に歯周ポケットと呼ばれる空隙が生じます。この歯周ポケットには更に細菌が増えるため、歯肉はより強く炎症を起こし、さらに出血が生じやすくなります。歯周病が進行すれば、歯ぐきだけでなく歯槽骨までもが破壊され、歯が動揺して出血が起こりやすくなります。
一方、口内炎はウイルス感染などを原因とした口腔粘膜の炎症で、口の中にただれやびらん、潰瘍が生じ、出血を伴うことがあります。口内炎ではウイルス感染による局所的な細胞傷害や、免疫異常によって粘膜が炎症を起こし、出血が生じます。粘膜の浮腫と炎症により出血が起こりやすくなっています。
このほか、外傷、血液疾患、腫瘍なども口の中の出血の原因となり得ます。例えば、物に噛みついたりした外傷、血小板減少症などの凝固異常、血管腫などの腫瘍形成が考えられます。
2. 発見方法と対策
口の中の出血がある場合、まず歯周病や口内炎などの口腔疾患の有無を確認します。次に外傷の痕跡がないか、血液検査で凝固異常がないか、腫瘍がないかなど、他の原因がないかを検索します。
対処としては、出血部位をタオルやガーゼなどで押さえる止血を行います。原因に対する治療が必要で、歯周病ではデンタルケアや歯石除去、口内炎では抗菌剤・抗炎症剤、凝固異常では血小板補充などが考えられます。出血が激しく止まらない場合は、止血剤の投与や出血部位の凝固処置も選択肢となります。
予防には、日頃の口腔ケアと定期健診が重要です。歯ブラシでのブラッシングや口腔洗浄を行い、異常がないか確認するようにしましょう。早期発見と適切な治療により、口の中の出血を予防できます。
3. 考えられる病気
- 歯周病
- 口内炎
- 扁平上皮がん
口の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の口内炎の主な原因はウイルス感染です。猫カリシウイルスやヘルペスウイルス、猫白血病ウイルスなどの感染が口内炎を引き起こします。
これらのウイルスは口腔内の粘膜細胞に感染・増殖することで局所的な細胞傷害と炎症反応を起こします。ウイルスに感染した部位の粘膜組織は壊死と潰瘍化を起こし、痛みや出血を伴う口内炎を発症します。ウイルス感染による口内炎では、舌、歯肉、口蓋といった口腔内の粘膜面が広範囲に炎症を起こし、ただれやびらんを形成します。
ウイルス感染による口内炎は、子猫の頃に母猫からの抗体がなくなる時期に発症しやすい傾向があります。また、糖尿病や腎疾患などによる免疫力低下が口内炎の誘因となることもあります。これらの病気ではウイルス感染に対する抵抗力が低下しているため、ウイルスの感染・増殖が容易となりやすいためです。
歯垢や歯石の蓄積、栄養不良なども口内炎のリスクを高める因子として知られています。これらは口腔内の衛生状態を悪化させ、ウイルス感染の温床となりやすいからです。
2. 発見方法と対策
口内炎が疑われる場合、まず口の中のただれやびらん、出血などの有無を確認します。次に全身状態の観察で免疫力低下を示唆する症状がないかを確認し、必要に応じて血液検査などを行います。
対策としては、原因ウイルスに対する治療が基本です。抗ウイルス薬の投与やワクチン接種を行います。併発している疾患も治療し、栄養管理で体力をつけることも大切です。口腔内の清潔保持も重要なケアとなります。ガーゼや歯ブラシを用いてのブラッシングが有効です。
予防にはワクチン接種と日頃の口腔管理が有効です。定期的な歯科検診も予防に役立ちます。
3. 考えられる病気
- 口内炎
- 猫風邪(猫の上部気道感染症:猫カリシウイルス、猫鼻気管炎(ヘルペス)ウイルス、クラミジア・フェリス)
口の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫のよだれが多い症状の主な原因は、下記の通りです。
1つ目は、口内炎や歯周病などの口腔疾患です。これらの疾患では口腔内の炎症により痛みが生じ、よだれの分泌量が増えます。口内炎はウイルス感染により口腔粘膜が炎症を起こし、歯周病は歯垢に含まれる細菌の感染で歯肉に炎症が生じます。いずれも炎症による疼痛刺激で唾液分泌が亢進し、よだれが多く出やすくなります。
2つ目は、食道炎や胃炎、胃潰瘍などの消化器疾患です。これらは嘔吐を繰り返す原因となり、その際によだれが多く出ます。消化管の傷害や刺激は嘔吐反射を引き起こし、それに伴って唾液分泌が増加するためです。
3つ目は、猫風邪や熱中症などで体温が上昇した場合です。体温上昇により唾液分泌が亢進し、よだれが出ます。体温調節のために唾液の蒸散作用を利用する反応の結果と考えられます。
4つ目は、中枢神経疾患による流涎(唾液過多)です。これは原因や機序が不明な流涎症と、中毒や脳疾患など他の病気に伴う二次的な流涎があります。
このほか、ストレスなどがよだれの増加を招く場合もあります。ストレス性の唾液分泌亢進が生じるためです。
2. 発見方法と対策
よだれが多い場合は、口腔内の異常の有無を確認します。次に体温を測定し、消化器症状や神経症状がないかを観察します。場合によっては血液検査や画像検査を行い、原因疾患の診断を行います。原因不明の流涎(唾液過多)の場合は、MRI等の画像検査が診断の手掛かりとなります。
対策としては、原因疾患の治療が基本となります。口腔疾患であれば口腔内の治療、消化器疾患では胃腸の治療、中枢神経疾患では原因究明と対症療法などが必要です。ストレス対策も大切な予防法の1つです。飼育環境の調整や鎮静剤の使用等が考えられます。
3. 考えられる病気
- 口内炎
- 食道炎
- 胃拡張・胃捻転
- 巨大食道症(食道拡張症)
- 猫風邪(猫の上部気道感染症:猫カリシウイルス、猫鼻気管炎(ヘルペス)ウイルス、クラミジア・フェリス)
- 熱中症
- 中毒
口の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
歯の症状
1. 原因と傾向
猫の歯ぐきの腫れは、主に歯周病が原因となっています。歯周病は歯垢に含まれる細菌感染が引き金となって発症し、初期には歯肉炎を起こします。
歯肉炎では歯垢中の細菌が歯肉に感染・増殖することで、歯肉が炎症を起こして赤く腫れあがります。歯垢には多くのグラム陽性・陰性菌が含まれており、その中でもビブリオ属菌やポルフィロモナス属菌などが歯肉炎の主な原因菌です。これらの細菌感染とそれに対する宿主の炎症反応が歯肉の腫脹をもたらします。歯肉が腫れると歯ブラシでのブラッシングが困難になり、さらに細菌感染が進行。最終的には歯槽骨まで破壊される重度の歯周炎を引き起こします。
歯肉の腫れは歯周病の初期症状と言え、放置すると口臭や歯のゆるみ、歯の喪失に至る可能性があります。免疫力の低下やストレスも歯肉の腫れを引き起こしやすい因子です。これらは宿主の抵抗力を下げ、細菌感染を助長するためと考えられています。
2. 発見方法と対策
歯ぐきの腫れがある場合は、まず歯肉炎や歯周炎がないか確認します。歯垢の付着状況や歯の動揺を観察し、必要に応じてレントゲン検査で歯槽骨の状態を確認します。歯周ポケットの深さ計測も重要な検査です。
対策としては、専門的な歯科処置に加え、日頃からの口腔清潔の保持が重要です。ブラッシングの徹底により細菌感染を抑え、歯周病の進行を防ぎましょう。ストレス対策もポイントの1つです。早期発見と対処が歯肉の腫れの改善に有効です。定期的な検診で異常を見逃さないことも大切です。
3. 考えられる病気
- 歯周病
歯の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の歯ぐきが白くなる主な原因は、主に貧血によるものです。
貧血は赤血球数の減少やヘモグロビンの低下により、体の組織への酸素供給が不足する状態です。貧血があると歯ぐきの色素が失われ、蒼白な紅色になります。これは貧血によって歯ぐきの微小循環が障害され、歯ぐきの血色素であるヘモグロビンの量が減少することで起こります。
貧血を引き起こす代表的な疾患として、出血性疾患、汎血球減少症、溶血性貧血などがあります。出血の原因となる外傷、血液疾患、寄生虫症などによって貧血が生じ、歯ぐきが白くなります。慢性的な出血ではヘモグロビンの産生が追いつかず、貧血を来たしやすいです。
猫伝染性貧血や腎不全に伴う貧血でも歯ぐきの白変化が見られるため、歯ぐきの色から貧血の有無を推測できます。貧血に共通する症状の1つとして捉えることができます。
2. 発見方法と対策
歯ぐきの白変化がみられた場合は、まず貧血の有無を血液検査で確認します。赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値等を測定し、貧血の程度を判断します。次に貧血の原因を特定するため、出血や寄生虫症などの有無を確認していきます。
対策としては、貧血の原因疾患を特定し、それに対する治療を行うことが基本です。鉄剤の投与や輸血による貧血の改善も重要です。原因究明と対策により、歯ぐきの色調は回復するはずです。定期健診での歯ぐきの観察も早期発見につながります。
3. 考えられる病気
- ヘモバルトネラ症(猫伝染性貧血)
歯の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
耳の症状
1. 原因と傾向
猫がよく耳をかく原因はさまざまですが、主には以下の3つが挙げられます。
1つ目は、耳ダニなどの寄生虫感染です。耳ダニが外耳道に寄生すると、ダニの活動とそれに対する宿主の反応によりかゆみが生じ、猫は耳をかいてこれを抑えようとします。耳ダニは接触感染するため、飼い主は猫の耳ダニ感染を疑った場合、ほかの猫の感染有無にも注意が必要です。
2つ目は、外耳炎・中耳炎などの耳の疾患です。細菌や真菌による炎症でかゆみが生じ、耳かきを誘発します。外耳炎の原因としては耳ダニ以外にも異物の侵入や水分の影響などが考えられます。炎症により耳道内が腫脹することで、かゆみと耳かき行動が引き起こされます。
3つ目は、アレルギー反応です。食物や環境アレルゲンに対するアレルギーで、耳介の炎症とかゆみを起こし、耳をかく原因となります。アレルギー性耳炎では片側性に起こりやすいのが特徴です。
ストレスによる精神的なイライラも耳かきの誘因になると考えられています。ストレスで自律神経失調を来たし、耳血流の異常が生じて痒みを感じるためです。
このほか、耳石症など他の疾患でも同様の症状が現れることがあります。
2. 発見方法と対策
耳をかく場合は、まず耳の観察と聴診を行い、外耳道の異常や耳垢の有無を確認します。次に全身状態から原因を推定していきます。例えば、皮膚の粘膜症状からアレルギーを疑ったりします。
対策としては、原因疾患の治療が基本です。寄生虫感染なら駆除薬、外耳炎なら抗生物質、アレルギーなら除去や薬物療法、ストレスなら環境調整等が適宜選択されます。
予防には清潔な耳の保持とストレス軽減が重要です。定期的な検診も早期発見につながります。
3. 考えられる病気
- 外耳炎
- 耳ダニ感染症(耳疥癬、ミミヒゼンダニ感染症)
- 耳血腫(耳介血腫)
耳の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の耳垢が多い主な原因は外耳炎です。
外耳炎は耳ダニや細菌・真菌などにより外耳道が炎症を起こす疾患です。外耳炎があると、炎症に対する防御反応として耳垢の分泌が増加します。
具体的には、外耳炎の原因となる耳ダニが外耳道で活動することで宿主の過敏反応が引き起こされ、大量の耳垢が分泌されます。耳ダニは外耳道の表皮を食害することで刺激となり、反応性に耳垢腺からの分泌を増やします。
また、細菌や真菌による外耳炎でも、炎症に伴う免疫反応によって脂質成分が過剰に作られ、湿った耳垢が多量にできます。細菌等に対する宿主応答の一環として過剰分泌が生じると考えられます。
外耳炎以外では、先天性の耳垢腺の発達異常などが原因の場合もありますが、ほとんどは外耳炎に関連していると考えられます。
2. 発見方法と対策
耳垢が多い場合は、まず外耳炎がないか外耳道を確認します。異常があれば、細菌培養等の検査で原因を特定し、耳ダニか細菌・真菌かを判断します。
対策としては、抗菌剤やノミ・ダニ駆除薬等で外耳炎の原因となる疾患を治療することが基本です。
なるべく清潔な外耳道の維持が管理のポイントとなりますが、耳垢を完全に取り除く様な強い耳掃除は避けるべきです。
定期的な耳のチェックと早期発見が予防のために重要です。
3. 考えられる病気
- 外耳炎
- 耳ダニ感染症(耳疥癬、ミミヒゼンダニ感染症)
耳の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の耳の中が赤く腫れる主な原因は外耳炎です。
外耳炎は、耳ダニや細菌、真菌等によって外耳道に炎症が起こる疾患です。これらの原因により、外耳道の粘膜組織が炎症を起こし、充血、腫脹、浮腫が生じて赤く腫れあがります。
具体的には、外耳炎の代表的な原因である耳ダニが外耳道内で活動し、外耳道粘膜を刺激することで赤みと腫れが引き起こされます。耳ダニは外耳道内で増殖する間に糞や体液を排出するため、これらがアレルゲンとなって外耳道の過敏反応を誘発します。
また、細菌や真菌による外耳炎でも、外耳道内の炎症性サイトカインの働きで血管拡張と血流増加、浮腫が起こり、赤く腫れた状態となります。特に真菌感染ではカンジダやアスペルギルスなどが外耳炎の原因となることが知られています。
外耳道の赤みと腫れは外耳炎の主要症状と言え、病初期から見られる重要な兆候です。炎症の程度によって赤みの強さは変化します。
2. 発見方法と対策
耳の中が赤く腫れている場合は、外耳炎を強く疑います。外耳道の観察では赤みと腫れの程度を確認し、原因の検索を行います。細菌培養等により原因菌を同定することも大切です。
対策としては、外耳炎の原因疾患に対する治療が基本となります。抗菌薬等の投与により炎症を抑え、腫れを改善させることが重要です。外耳道の清潔保持も管理ポイントの1つです。定期的なチェックで早期発見に努めましょう。
3. 考えられる病気
- 外耳炎
耳の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬が
2. 発見方法と対策
耳の
3. 考えられる病気
- 外耳炎
- 耳ダニ感染症(耳疥癬、ミミヒゼンダニ感染症)
- 耳血腫(耳介血腫)
耳の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
皮膚の症状
1. 原因と傾向
猫の皮膚が荒れる代表的な原因は、アレルギー反応、寄生虫、細菌やウイルスなどの感染症、代謝異常、外傷などがあげられます。
アレルギー反応では、食物アレルギーや吸入性アレルギー、接触性アレルギーなどが考えられます。例えば、特定の食べ物に含まれる成分に対して過敏反応を示す食物アレルギーでは、その食べ物を摂取した後に痒みを伴う皮膚炎が現れます。吸入性アレルギーでは、季節的に飛散する花粉などを原因として気管支喘息や皮膚炎が繰り返し生じます。接触性アレルギーでは、猫が触れる場所の床材や石鹸、シャンプーなどに含まれる成分がアレルゲンとなって皮膚症状を引き起こします。
寄生虫ではノミ、ダニ、ツメダニなどの寄生が皮膚症状を引き起こします。ノミの唾液に対する過敏反応がノミアレルギー性皮膚炎の症状を生み出します。疥癬はダニの寄生によって発生する皮膚炎です。猫ヒゼンダニやツメダニは皮膚に刺入・掻爬して皮下組織内を移動することから、その痕跡に沿って炎症・痒み・フケなどの症状が続発します。
感染症では、猫ひっかき病や猫カリシウイルス感染症などウイルス性の疾患や、膿疱性皮膚炎など細菌感染が原因となりえます。これらの感染に対する宿主側の過剰反応が結果として皮膚症状を呈することになります。膿疱性皮膚炎では表皮下に膿瘍を形成することが特徴的です。
代謝異常では甲状腺機能低下症が代表例です。甲状腺ホルモンの低下によって皮膚や被毛の代謝機能が低下し、脱毛や皮膚の乾燥、脂漏性皮膚炎などを生じます。
外傷に関連しては日焼けや熱傷も皮膚を荒らす要因となります。屋外での長時間曝露などによって起こる日焼けは脱水状態を招き炎症を起こしやすくします。熱傷はその部位の水分喪失と表皮・真皮の壊死を生じさせます。
これらの原因で皮膚症状が出現しやすいのは、免疫力が低下しがちな子猫や老猫です。成猫で発症する場合も、何らかの基礎疾患を有することが多いと考えられています。例えば猫白血病や猫免疫不全ウイルスへの感染が免疫抑制状態を生み出し、二次的に種々の皮膚疾患を引き起こすことが知られています。
2. 発見方法と対策
皮膚の異常を早期に発見するには、普段から全身の皮膚を細かくチェックすることが大切です。気になる部位がないか、痒みや炎症の兆候はないか、両側性か片側性かなど観察するポイントは多岐にわたります。皮膚の状態だけでなく、被毛の様子や関節の可動域にも注意が必要です。
例えば、毛づやが薄い場所や脱毛している場所はないかを探します。脂漏性皮膚炎では脂漏性脱毛を呈することが多く、甲状腺機能低下症を疑わせる所見のひとつです。関節リウマチでは四肢の可動域制限から始まることがあるため、四肢の動きの様子も観察します。これら関連所見から病態を推測していくことが大切です。
季節性アレルギーの場合、特定の季節に症状の増悪が認められます。一方で食物アレルギーでは季節性はありません。ある疾患への感染後に時間経過とともに症状が変化することも多く、状況に応じて観察すべきポイントも異なってきます。
いつもと違う症状がみられた場合は速やかに獣医師の診断を受けることをおすすめします。対策としては、原因疾患の治療を第一としますが、症状に応じて抗生物質やステロイドなどの投与、保湿ケアや食事調整などを適宜行っていきます。清潔な飼育環境の確保も忘れてはいけません。
例えば抗生物質は細菌感染症に対して用います。ステロイドは炎症性皮膚病変を抑える効果がある反面、感染症の治癒を妨げるデメリットもあるため、併用する抗生物質の選択が大切です。食事療法も原因に応じて除去食や水分補給を考慮していく必要があります。
3. 考えられる病気
- アトピー性皮膚炎
- アレルギー性皮膚炎
- ノミアレルギー性皮膚炎
- ツメダニ症
- ニキビダニ症(毛包虫症)
- 疥癬
- 好酸球性肉芽腫症候群
- 扁平上皮がん
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の発疹は、皮膚の炎症などを反映した痒みを伴う赤い発疹(ブツブツ)が現れる症状です。主な原因としては、アレルギー反応や寄生虫、ウイルス・細菌感染、代謝異常などがあげられます。
アレルギー性皮膚炎の場合、原因となる花粉やハウスダスト、食べ物などのアレルゲンに体質的に過敏に反応することで発疹が発症します。アトピー性皮膚炎では吸入アレルゲン、食餌性皮膚炎では食物アレルゲン、接触性皮膚炎では接触アレルゲンがそれぞれ症状を引き起こします。
ノミやダニにかかると寄生部位が発疹を起こすほか、ノミアレルギーで体中に広がるケースも。ノミアレルギーではノミの唾液中の抗原に対する過敏症が痒みと発疹の主因となっています。疥癬では猫ヒゼンダニそのものに対する免疫反応も発疹に関与していると考えられています。
感染症ではウイルスや細菌・真菌が発疹や炎症を引き起こします。マイコプラズマでも発疹を伴うことが見受けられます。
代謝異常では甲状腺機能低下症、副腎皮質機能低下症などで皮膚萎縮と脱毛、痒みを伴うことがあります。
これらの原因で発疹が出現しやすいのは、免疫機能が未熟な子猫や老齢猫が多い傾向にありますが、成猫でも基礎疾患に左右されたり季節的な要因などで発症することがあります。
2. 発見方法と対策
発疹の早期発見には全身の皮膚観察が欠かせません。いつもと様子が変わった際にどこが違うのかポイントを絞って観察します。
部位、範囲、出没パターンから考え得る原因の絞り込みが可能です。例えば両側対称性の範囲では代謝異常が疑われます。季節性発生では乾燥やアレルギーが疑われます。
治療は原因疾患の特定と対症療法の併用が基本です。アレルギー性皮膚炎では原因抗原の特定と回避、ステロイドの塗り薬や抗ヒスタミン薬の内服などで対応します。
寄生虫ではノミ・ダニ駆虫薬とともに抗アレルギー薬や抗炎症薬を併用し症状緩和を図ります。細菌・ウイルス感染では抗生物質や抗ウイルス薬の選択が重要視されます。
清潔な飼育環境と適度な日光浴も大切なポイントでしょう。住居内での飼育ではエアコンによる乾燥も発疹誘因となるため加湿にも気をつける必要があります。
3. 考えられる病気
- アトピー性皮膚炎
- アレルギー性皮膚炎
- ノミアレルギー性皮膚炎
- ニキビダニ症(毛包虫症)
- 疥癬
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の体がかゆい主な原因は、アレルギー反応、寄生虫、細菌・ウイルス感染などによる炎症性皮膚疾患です。
アレルギー性皮膚炎では体内のアレルゲンに対する過敏反応、寄生虫ではその寄生部位と全身への反応性がかゆみの原因となります。食餌性、吸入性、接触性とアレルギーのタイプは様々ですが、いずれも免疫グロブリンE(IgE)を介したアレルギー反応の結果として痒みを感じます。
細菌・ウイルス感染では皮膚への菌体成分や炎症性サイトカインなどの作用機序が考えられます。
発生部位は病型によって多様ですが、自傷行為による二次的な皮膚炎を併発することも少なくありません。基礎疾患を有する成猫ほど重症化しやすい傾向が見受けられます。
2. 発見方法と対策
かゆみへの対応は発見が重要です。普段の様子との違いに注目し観察ポイントを絞ることが早期発見につながります。
治療面では原因疾患特定と対症療法を並行します。抗炎症薬や抗アレルギー薬の使用に加え、保湿と清潔な飼育環境の確保が欠かせません。必要に応じ食事療法も視野に入れます。
保存的治療で改善しないような難治性の症例では免疫抑制剤の使用やアレルゲン免疫療法(減感作療法)の適用も考慮されます。
3. 考えられる病気
- アトピー性皮膚炎
- アレルギー性皮膚炎
- ノミアレルギー性皮膚炎
- ニキビダニ症(毛包虫症)
- 疥癬
- 好酸球性肉芽腫症候群
- 日光皮膚炎
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫のフケが多い代表的な原因は、アレルギー性皮膚炎、寄生虫感染、細菌・真菌感染などです。
アレルギー性皮膚炎では、体内のアレルゲンに対する過敏反応によるかゆみで、猫がしきりに掻爬行為を行うことでフケが増加します。主なアレルゲンとしてはノミや食物、ハウスダストなどが知られています。
ノミやダニなどの寄生虫感染では、寄生部位に生じる皮膚の剥離や浸出液がフケとなって見られるほか、二次的な細菌感染による湿疹形成でもフケが伴います。
細菌や真菌による表在性皮膚感染症では、病変部からの浸出液や化膿性分泌物、表皮剥離などがフケとして現れることがあります。代表的な細菌感染として膿疱性皮膚炎、真菌感染として皮膚糸状菌症があげられます。
これらの病型では二次的な感染による病変の広がりが起こりやすく、フケが多い範囲も拡大していきます。基礎疾患がある高齢猫ほど重症化するリスクが高いと考えられます。
2. 発見方法と対策
フケの増加は様々な皮膚疾患の共通する重要な手がかりの一つです。
まずフケが見られる部位と範囲、出没パターンに着目します。季節性・慢性化の有無などから考え得る原因疾患の絞り込みが可能です。
次に治療面では、推定される原因疾患に対する対策を第一としつつ、フケをともなう病変部位の清掃や付着皮膚の除去を行います。抗生物質や薬浴による対症療法も並行して行っていきます。
清潔な飼育環境の確保も再発予防には欠かせません。第二次感染を防ぐ意味でも重要なポイントといえるでしょう。
3. 考えられる病気
- アレルギー性皮膚炎
- ツメダニ症
- ニキビダニ症(毛包虫症)
- 皮膚糸状菌症(白癬)
- 疥癬
- 日光皮膚炎
- スタッドテイル(尾腺炎、尾腺過形成)
- 好酸球性肉芽腫症候群
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫にしこりやはれができる代表的な原因疾患としては、腫瘍性疾患、感染症、外傷等に伴う炎症、代謝異常等があげられます。
例えば乳腺腫瘍、肥満細胞腫、膿瘍などの良性・悪性腫瘍がしこりの原因となります。このうち乳腺腫瘍は中高年齢のメスに好発する一方、肥満細胞腫は若齢でも発生しうる腫瘍です。膿瘍は局所の細菌感染に対する宿主の過剰反応が原因といえます。
細菌・真菌感染では炎症を反映して腫脹が生じます。代表的なものとしては蜂窩織炎、クリプトコッカス症等があげられます。これらは二次感染による重症化が懸念される疾患です。
外傷後の瘢痕組織の形成でもしこりを触知することがあります。こちらは様々な病態をともなうことがあるため注意が必要です。
好発部位は原因疾患によって異なりますが、皮下組織や粘膜下組織、臓器など様々な部位でみられることが特徴です。
2. 発見方法と対策
しこりの早期発見には体表の細かな観察が欠かせません。いつもと違うつぶつぶ感がないか確認します。
部位と範囲、触診時の硬さや可動性などの性状から原因疾患の推定が可能です。例えば乳腺腫瘍では柔らかさと可動性が特徴です。
治療面では外科的切除が第一選択となることが多いですが、放射線治療や薬物療法を併用する場合もあります。切除不能や転移を有する症例ではこれらの併用が重要視されます。
蜂窩織炎やクリプトコッカス症等の病原菌が引き起こす感染症においては、原因菌に有効な抗菌薬を投与するのが効果的です。
清潔な飼育環境の確保も二次感染予防のために大切なポイントです。
3. 考えられる病気
- クリプトコッカス症
- 脂肪織炎(黄色脂肪症、イエローファット)
- 水腎症
- スタッドテイル(尾腺炎、尾腺過形成)
- 好酸球性肉芽腫症候群
- 乳腺腫瘍
- 肥満細胞腫
- 子宮がん
- 扁平上皮がん
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の皮膚がうすくなる代表的な原因は、副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)、甲状腺機能低下症、栄養失調などです。
クッシング症候群では副腎皮質から過剰に分泌されるホルモン(コルチゾール)の影響で皮膚の萎縮と弾力性低下が起こります。甲状腺機能低下症でも皮膚代謝異常が皮膚の変化を引き起こします。
栄養失調は様々な全身疾患や消化器疾患、飼育環境の問題などが背景にあると考えられます。栄養状態の悪化は皮膚を構成するコラーゲンや毛包組織の生成を低下させる結果、皮膚萎縮・脱毛へとつながります。
加齢の影響も皮膚の変化に拍車をかけると考えられます。
2. 発見方法と対策
皮膚自体の性状変化に注目します。具体的には皮膚のうすさ加減や弾力性低下、血管の透見状態を確認します。これらの所見から原因疾患の絞り込みが可能です。
治療面では原因疾患に対する根本的治療を第一とします。場合によっては栄養補助食品の投与やステロイド外用薬による対症療法も有用です。
皮膚の状態から UV 過敏症も懸念されるため、日光過敏対策も重要なポイントといえます。
3. 考えられる病気
- クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の皮膚や粘膜の黄疸は、胆汁うっ滞を反映しています。胆汁に含まれるビリルビンが過剰に蓄積した結果、このような症状が現れます。
黄疸を来す代表的な疾患としては、肝炎、肝硬変、胆石症、胆道炎、膵炎などの肝胆道系疾患があります。これらは中高年齢で発症しやすい傾向にあります。
また先天性代謝異常症として胆道閉鎖症も黄疸の原因となりえます。この病態は生後数日から数ヶ月以内に黄疸を発症するのが特徴です。
これら疾患では肝臓や膵臓など肝胆道系臓器の機能不全や閉塞に伴い、胆汁の流れが阻害されて黄疸となります。慢性肝炎では肝実質細胞の壊死と繊維化の進行で黄疸が現れます。
2. 発見方法と対策
黄疸が進むと皮膚や目の白いところが黄色く見えるようになります。他の自覚症状はあまり発生しないため、普段から眼や口腔内の観察が必要です。皮膚は光で確認しにくいので口腔内に注目します。
発見後は速やかに肝臓や膵臓などの検査を行い、根本治療に取り組みます。症状に応じて補液、緩下剤投与などの対症療法も併用します。
日頃から適度な運動と過食防止が黄疸予防に効果的です。定期健診で早期発見にも努めましょう。
3. 考えられる病気
- トキソプラズマ症
- 肝リピドーシス(脂肪肝)
- 肝炎(胆管炎、胆管肝炎、肝硬変)
- 猫伝染性腹膜炎
- 糖尿病
- ヘモバルトネラ症(猫伝染性貧血)
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
チアノーゼ(皮膚や粘膜の青紫色化)は、酸素不足により血中の還元ヘモグロビンが増加することで起こります。主な原因としては、呼吸器系や心血管系の疾患が考えられます。呼吸器系の疾患では気管支炎や喘息、肺炎などにより肺胞内酸素分圧が低下し、心血管系の疾患では心不全に伴う肺水腫や心室中隔欠損症などにより組織への酸素供給量が低下することでチアノーゼが生じます。
チアノーゼを起こしやすい傾向にある猫としては、先天性の心疾患や気管や気管支の疾患を持つ猫、喘息など呼吸器系の疾患を抱えている猫などがあげられます。特に先天性心疾患のある猫は症状が重症化しやすいため、チアノーゼが生じるリスクが高くなっています。また、被毛が薄いスフィンクス種の猫の場合は皮膚の血管が透けて見えやすいため、軽度のチアノーゼでも発見しやすい特徴があります。
高齢の猫や子猫は全身状態が弱っていることが多く、感染症などで呼吸器系や心血管系の症状を起こした際、チアノーゼを伴いやすい傾向にあります。妊娠中や出産直後の母猫も同様に全身の状態が弱っており、産後の感染症などで呼吸器系の疾患を併発するとチアノーゼを起こすことがあります。
さらに胸腔内に気胸や胸水がたまった状態でも、肺の機能が制限されて酸素化された血液量が低下するためチアノーゼを起こします。また胸腔内の炎症による胸膜癒着で肺の拡張が妨げられる場合も同様です。体外から圧迫が加わっている状況でもチアノーゼが現れることがあり、例えば交通事故などで肋骨骨折を起こした際に生じる呼吸困難や、喉頭浮腫による気道閉塞などで二次的にチアノーゼが見られることがあります。
アナフィラキシーショックで血圧が極端に低下する状況でもチアノーゼを起こす可能性があります。全身状態が不安定な時期にチアノーゼが見られると、症状がより重篤化することが多いため、早期の対応が欠かせません。
2. 発見方法と対策
チアノーゼの主な症状は、鼻腔粘膜、口腔粘膜や舌、眼の粘膜、耳介周囲などが青紫色に変色することです。このほか、動悸や呼吸困難などを伴うこともあります。
チアノーゼは呼吸器系や心血管系の疾患に起因する二次的な症状であることが多いため、可能な限り早期発見に努めることが大切です。毎日の健康チェックの際や、顔を近くで観察する機会を作るなどして、少しでも異変を感じたら速やかに獣医師の診療を受けることをおすすめします。
チアノーゼが確認された場合は、原因疾患の治療を最優先します。原因である呼吸器系や心血管系の疾患を改善することができれば、多くの場合、チアノーゼも改善されます。
急性期の対応としては、酸素吸入や点滴補液などで全身状態を安定させるとともに、致死的な心不全や呼吸不全を防ぐことが大切です。チアノーゼを伴う呼吸困難な場合は速やかに呼吸補助を行う必要があり、気管内挿管や人工呼吸器の使用など、集中治療室での管理が必要になることも少なくありません。
薬物療法としては、気管支拡張薬や利尿薬を使用して呼吸機能改善や水腫を軽減させ、血中酸素の増加を図ります。循環不全に対する強心薬投与や、輸血による酸素運搬能改善も有効です。
チアノーゼ発症の予防には、基礎疾患となりうる心疾患や気管支疾患、喘息への早期発見と適切な対応が欠かせません。定期的な健康診断を心がけ、異常を感じた際には躊躇なく受診することが大切です。予防策として、猫用ワクチンの接種や呼吸器感染症対策も有効的です。
3. 考えられる病気
- 喘息(慢性気管支炎、アレルギー性気管支炎)
- 膿胸
- 先天性心疾患
- リンパ腫
- 熱中症
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
被毛の症状
1. 原因と傾向
猫の抜け毛は、季節変化に伴う生理的な脱毛と、病気に起因する病的な脱毛の2つに大別されます。
生理的な脱毛は、季節の変わり目(換毛期)に見られるものです。この場合抜け毛の量は多くなりますが、新しい毛が生えてきて自然に改善されます。脱毛部位は体のあちこちに散発的に起こることが多く、四肢や腹部ではなく体側部で起こりやすい傾向があります。
一方、病的な脱毛の主な原因として、皮膚疾患や内分泌疾患、寄生虫病、栄養障害などがあげられます。代表的な皮膚疾患ではアレルギー性皮膚炎、ノミアレルギー性皮膚炎、疥癬、皮膚糸状菌症などに伴うかゆみとそれに対する自己傷害が脱毛の原因となります。
内分泌疾患では甲状腺機能亢進症や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)などのホルモン異常が脱毛の原因となることがあります。これらの内分泌疾患では左右対称性の脱毛パターンを示すことが多いです。
高齢猫や病弱な猫は栄養状態の低下なども脱毛の原因となり得ます。こうした場合、飼い主による毛づくろいなどの手入れや、ストレスの軽減が脱毛抑制に有効です。
このほか、胸腺腫瘍に代表される悪性腫瘍では全身状態の悪化により脱毛が引き起こされることがあります。放射線療法や化学療法などによる腫瘍の制御が必要となります。
皮膚寄生虫であるツメダニやニキビダニの寄生によって局所的な脱毛が引き起こされることもあり、寄生虫駆除が脱毛の治療になります。
2. 発見方法と対策
脱毛を発見した場合、まず最近の飼育環境の変化に注意し、生理的な脱毛なのか病的な脱毛なのかを見極める必要があります。体重減少や皮膚症状を伴う場合は病的な脱毛の可能性が高いです。
次に脱毛部位とそのパターンから疾患の推定に努めます。対称性の脱毛は内分泌疾患を疑わせます。一方、痒みに伴う自己傷害は皮膚疾患に起因することが多く、寄生虫疾患も疑うべきです。局所的な脱毛と体重減少からは、腫瘍も疑う必要があります。
脱毛の対処としては、可能な限り原因疾患の特定と治療が必要です。対症療法としては皮膚の保湿、炎症および痒みの抑制が有効的です。栄養管理や愛猫への毛づくろいによるケアも脱毛抑制に大切な役割を果たします。
生理的な脱毛では、新しい毛の再生を待つ以外に対処方法はあまりありません。しかし、皮膚の乾燥を防ぐ保湿ケア、栄養状態の維持などが新しい毛の再生を助けると考えられています。
3. 考えられる病気
- アトピー性皮膚炎
- アレルギー性皮膚炎
- ノミアレルギー性皮膚炎
- 日光皮膚炎
- 疥癬
- ツメダニ症
- ニキビダニ症(毛包虫症)
- 皮膚糸状菌症(白癬)
- スタッドテイル(尾腺炎、尾腺過形成)
- クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
- 好酸球性肉芽腫症候群
- 扁平上皮がん
被毛の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の毛ヅヤが悪くなる主な原因として、栄養状態の低下や内分泌異常、皮膚疾患などがあげられます。
成長期や妊娠・授乳期の栄養需要の高い時期に摂取栄養が不足すると、皮膚や被毛の健康状態を維持できなくなり、毛ヅヤの低下を招きます。食事内容の改善や毛づくろいなどのケアで栄養状態を高めることが毛ヅヤ回復に重要です。
甲状腺機能亢進症や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)などの内分泌異常では脱毛や被毛の乾燥が起こりやすく、毛ヅヤの低下が見られます。これらの疾患に対する薬物治療が毛ヅヤの回復に有効です。
皮膚疾患では、自己傷害に伴う炎症や感染症といった二次的な要因によって被毛の健康状態が損なわれ、脱毛や潰瘍などが生じて毛ヅヤが低下します。皮膚疾患への治療と併用した皮膚の保湿ケアが必要です。
高齢猫では体力の低下に伴って自ら体をなめる頻度が低下し、老廃毛が増加してしまうことも毛ヅヤ低下の原因となります。飼い主によるブラッシングとトリミングが老廃毛の除去と新しい毛の再生を促し、毛ヅヤの維持につながります。
過度な日光浴は皮膚や毛根を障害し、皮膚炎や毛周期の乱れを生じさせて毛ヅヤ低下を招く場合があります。猫を屋外で遊ばせる際には、日差しの強すぎる日は避けるなど注意が必要です。
2. 発見方法と対策
毛ヅヤの低下は視診や毛づくろいの際に確認できます。頭部や背中を中心に、全身的か部分的かを観察します。脱毛や皮膚炎を伴う場合は病的な毛ヅヤ低下を疑います。
栄養状態の改善、基礎疾患の治療に加えて、皮膚の清潔保持や適度な保湿が毛ヅヤ向上に大切です。市販の皮膚塗り薬・被毛サプリメントの投与も有効的な場合があります。
食事内容をチェックし過不足がないか確認します。散歩中の日光浴を避けるなど紫外線対策も効果的です。定期的なブラッシングとトリミングで老廃毛を取り除き、新しい毛の再生を促します。
3. 考えられる病気
- 回虫症
- 甲状腺機能亢進症
- 胃腸炎
- 糸球体腎炎
- 慢性腎不全
被毛の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
呼吸器の症状
1. 原因と傾向
猫が咳をする症状の背景には、気道系の炎症や呼吸器感染、気道の異物が含まれることが多いです。ウイルスや細菌、寄生虫による炎症反応が代表的ですが、アレルギー性疾患や腫瘍に伴う二次的な咳も少なくありません。
ウイルス感染症ではカリシウイルスやヘルペスウイルスが主な原因となり、風邪様の症状を示しながら気管支への炎症が広がることで咳が生じます。細菌感染では気管支炎から肺炎への移行に伴って咳が認められることが多いです。免疫力が低い子猫や老猫が発病すると重症化することが多く、場合によっては命を落とす危険性もあります。
寄生虫症では回虫や肺虫などの線虫類が肺内で幼虫移行を起こし、機械的刺激によって咳が引き起こされます。
喘息やアレルギー性気管支炎の急性増悪期にも咳が頻発します。また気道腫瘍の進展に伴う気道狭窄でも咳が生じることがあります。
一方で、基礎疾患なしに誤嚥などの物理的刺激で気道反射が亢進して慢性の咳を来すこともあり、精査が必要です。
2. 発見方法と対策
咳をして呼吸状態の変化を示すときは早急な受診が望まれます。発作的な咳に加えて呼吸が浅く、呼吸困難を示す場合には重篤な呼吸器感染症を疑うべきです。
まず体温測定と聴診によって肺炎などの有無を確認する必要があります。次いで気道の炎症や感染症を測定する検査を実施し、精査していきます。
原因疾患の種類や重症度に応じて、抗生物質や駆虫薬、抗アレルギー薬や気管支拡張薬といった薬物療法を選択し、併せて基礎疾患に対する治療を行っていきます。
猫風邪にはワクチン接種も推奨されますが、ワクチン接種をしていても感染を完全に防ぐことはできません。ただし、免疫をつくることで重症化を防ぎ、軽い症状ですむ可能性が高くなります。
飼育環境の管理には細心の注意が必要であり、清潔な水や適温などを常に保つことが肺炎などの合併症予防にもつながります。
咳が慢性化した場合はステロイド療法を考慮しますが、原因の追及に努め、漫然と使用し続けないよう注意が必要です。
3. 考えられる病気
- トキソプラズマ症
- フィラリア症(犬糸状虫症)
- 回虫症
- 猫風邪(上部気道感染症:猫カリシウイルス、猫ヘルペスウイルス、クラミジア)
- 気管支炎
- 喘息(慢性気管支炎、アレルギー性気管支炎)
- 膿胸
- 肺炎
- 巨大食道症(食道拡張症)
- 先天性心疾患
- 心筋症
- リンパ腫
呼吸器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の「ゼーゼー苦しそう(呼吸が荒い)」症状の原因としては、喘息、気管支炎、肺炎、心疾患などの呼吸器系や循環器系の疾患があげられます。これらの疾患は、ウイルスや細菌感染、ほこりや花粉などのアレルゲン、心臓の異常など、様々な要因によって引き起こされます。
具体的には、喘息は気管支に炎症が起こり気道が収縮することで発症します。気管支炎や肺炎はウイルス感染後に、細菌や真菌が二次感染した結果として起こることが多いです。心疾患では、生まれつきの心臓の形成異常や心筋症などにより心機能が低下し、全身の臓器に十分な酸素が供給されなくなって、各臓器の機能が低下します。
発症しやすい傾向としては、子猫や高齢猫は免疫力が弱いため重症化しやすく、先天性の病気を抱えている猫は症状が重くなりやすいです。また、太っている猫や短頭種の猫は呼吸機能が本来低下しているため呼吸器疾患にかかりやすく、体力の弱っている猫も重症化しやすいです。ストレスも症状を悪化させる大きな要因となります。
喘息では、ほこり、花粉、食べ物などのアレルゲンが気道支を刺激して発症するアレルギー性喘息が主ですが、原因不明の喘息も多いです。近年、室内で過ごす猫が増えたことで、室内アレルゲンによる喘息が増加していると考えられています。
気管支炎や肺炎では、冬場に空気が乾燥することで気道の防御機能が低下し、感染しやすくなることが知られています。寒冷や乾燥は呼吸器疾患の悪化要因となるため、注意が必要です。
2. 発見方法と対策
苦しそうな呼吸をしている猫を発見した場合、まず落ち着いて猫の様子を観察します。嘔吐や下痢など他の症状がないか、食欲低下はないかを確認しつつ、呼吸のリズムや深さにも注意を払い、呼吸困難の程度を判断します。
呼吸回数が増加していたり、口を大きく長時間開けているようであれば、呼吸困難が進行している証拠です。この場合は速やかに最寄りの動物病院を受診します。
受診後はレントゲン撮影や血液検査を行い、原因疾患の特定に取り組みます。特定でき次第、酸素投与や薬剤投与などの適切な治療を開始します。
治療と並行して、清潔で快適な環境を提供し、栄養管理にも気をつけます。ストレスが症状を悪化させることがあるので、なるべく猫を穏やかな状態に保つことが大切です。
治療期間中は定期的に診察を受け、症状の改善状況を確認していきます。原疾患に対する治療を適切に行うことで再発予防にもつながります。猫とともに治療生活を送る中で、気づいた症状の変化をできるだけ獣医師に報告しましょう。
3. 考えられる病気
- トキソプラズマ症
- フィラリア症(犬糸状虫症)
- ヘモバルトネラ症(猫伝染性貧血)
- 猫伝染性腹膜炎
- 鼻炎
- 副鼻腔炎
- 喘息(慢性気管支炎、アレルギー性気管支炎)
- 膿胸
- 肺炎
- 胃拡張・胃捻転
- 巨大食道症(食道拡張症)
- 横隔膜ヘルニア
- 先天性心疾患
- 心筋症
- リンパ腫
- 熱中症
呼吸器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
消化器の症状
1. 原因と傾向
猫が吐いてしまう症状(嘔吐)の原因としては、様々なものが考えられます。
まず、食事に関する要因です。例えば、腐った食べ物を食べてしまった場合や、人間の食べ物で猫にとって有害な成分を含むものを食べてしまった場合に嘔吐が起こります。急激な食事の変更も原因の1つです。食べ物アレルギーがある個体では、アレルゲンを含む食品を摂取した場合に嘔吐を伴う胃腸障害が現れることがあります。
次に、感染症です。ウイルスや細菌、原虫等の感染による消化器系への影響で、嘔吐が引き起こされることがあります。代表的なものとしては、猫パルボウイルス感染症、トキソプラズマ症等があります。これらの感染症では、病原体が小腸や胃の粘膜細胞を障害することで消化吸収機能が低下し、嘔吐や下痢などを招くと考えられています。また、寄生虫である回虫や条虫の感染でも嘔吐を伴うことがあります。
さらに、毛玉が原因である場合も少なくありません。猫は体をなめる際に自身の毛を飲み込んでしまうことがあり、その毛が胃の中でもつれ合って固まった毛玉ができてしまうことがあります。この毛玉が胃粘膜を機械的に刺激したり、幽門を物理的に閉塞したりすることで嘔吐症状が引き起こされます。特に長毛種の場合は要注意です。
加えて、薬物中毒や食中毒、熱中症等も嘔吐症状の原因となり得ます。身の回りにある薬品等を誤飲したり、猫に有害な食べ物を食べてしまったりした場合に起こることがあります。これらの原因では、有毒物質による消化管障害や、過度の熱刺激に対する生体反応として嘔吐が生じると考えられています。
以上が主な原因ですが、そのほかにも腫瘍等の病気が関係している場合もあり、嘔吐を来たす要因は様々です。嘔吐の傾向としては、感染症の場合は発症直後から頻回に起こることが多い一方で、毛玉等の物理的原因ではゆるやかに出現することがあるなど、原因によって異なる点があることに留意する必要があります。
2. 発見方法と対策
猫の嘔吐の兆候を見逃さないことがとても大切です。普段から様子をよく観察し、元気がない、食欲不振等の異変があれば嘔吐の前触れである可能性があり、要注意です。
発見方法としては、まず嘔吐自体を実際に目撃することが最も確実です。頻度、吐かれた物の性状、その前後の様子等をできるだけ詳細に記録することが大切です。これにより嘔吐の慢性化や原因の特定に役立ちます。次に体重の減少です。これも長期にわたる嘔吐の結果である可能性があります。そのほか、水を飲む頻度が増えたり、下痢や便秘を伴ったりする場合も多く、これらの症状も併せて確認する必要があります。このように複数の症状を総合的に判断することで、嘔吐の原因や程度を推測する手がかりになります。
対策としてまずは動物病院での検査が不可欠です。画像検査や血液検査等によって原因の特定に努め、的確な治療を開始することができます。次に食事に関する注意が必要です。嘔吐が収まるまで水分を優先し、食べ物は消化の良いものを少量ずつ与える等、胃腸を休める食事管理が重要です。また、ストレスが原因の可能性があれば、引っ越しや飼い主の留守等、環境の大きな変化を避ける等の予防策も有効です。さらに根本的対策として、適切なワクチン接種や飼育環境の調整等を行うべき場合もあり、獣医師の指示に従うことが大切です。
3. 考えられる病気
- フィラリア症(犬糸状虫症)
- 回虫症
- 条虫症
- トキソプラズマ症
- 白内障
- 緑内障
- 甲状腺機能亢進症
- 食道炎
- 巨大食道症(食道拡張症)
- 胃腸炎
- 腸閉塞
- 横隔膜ヘルニア
- 猫伝染性腹膜炎(FIP)
- 膵臓炎
- 糸球体腎炎
- 慢性腎不全
- 急性腎不全
- 肝炎
- 脂肪肝
- 尿毒症
- 子宮蓄膿症
- 子宮がん
- 肥満細胞腫
- リンパ腫
- 糖尿病
- 毛球症
- 中毒
- 熱中症
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の食欲不振の原因は大きく分けて2つあります。1つは身体の病気や障害によるもの、もう1つはストレスなどの精神的な要因によるものです。
身体の病気による食欲不振の代表例は口内炎です。猫風邪などの感染症によって口の中が痛くなると、食べ物を飲み込むのがつらくなり、結果として食欲が減退します。ほかにも慢性腎臓病や肝臓病、膵臓病、消化器系の疾患など、体のさまざまな病気が食欲低下を引き起こすことがあります。中でも嘔吐や下痢などの消化器系の症状を伴う場合には、食事をとること自体がつらくなるため、食欲不振がより顕著に現れる傾向にあります。
消化器系以外でも代謝異常をきたす病気は食欲に影響します。例えば甲状腺機能低下症は基礎代謝が低下する病気ですが、これによって食欲が低下することがあります。逆に甲状腺機能亢進症は代謝が亢進する病気で、原因不明の食欲増加を来たすこともありえます。このように、代謝の変化が食事量の変化を引き起こす関係にあると考えられています。
一方で明らかな身体的な疾患が見当たらない食欲不振も少なくありません。これはストレスが主な原因と考えられています。引越しや同居猫の死など環境の変化に敏感に反応する猫も多く、不安やストレスが食欲低下を招くケースがよく見られます。猫は生来、環境の変化に敏感な動物で、小さな変化でもストレスが高まる傾向にあります。安心できる日常が崩れることで食欲が減退するメカニズムがあると考えられています。
食欲不振を訴える猫の特徴としては、高齢猫よりも若い成猫のほうが多い傾向にあります。ストレスに対する反応の違いが影響していると考えられています。若年性の猫ほど、生理機能が安定していないうえに環境変化への適応性が低いことが要因として挙げられます。一方で高齢猫はそもそも食欲が低下しやすい体質を持っていることが多いうえ、疾患による食欲不振も多く、高齢猫の食欲低下は日常的に見られる症状であることが多いです。
2. 発見方法と対策
食欲不振の兆候を見逃さないためには、猫の日頃の様子や行動パターンに注目し、いつもと違う点がないか気をつけて観察することが大切です。特に体重の減少は重要なサインなので、定期的に体重を測定して記録しておくことをおすすめします。体重や体脂肪の減少は食事量の低下を物語る最も確実な指標であり、このデータを定期的に記録しておくことは病状の進行を早期にキャッチするのに非常に有効です。
食欲不振が判明した場合は、速やかに獣医師の診断を受けることが重要です。原因となる病気の有無の確認に加え、脱水症状の有無もチェックします。必要に応じて輸液や栄養補給などの治療を開始します。食思不振が長引いている場合、脱水症状が見られることも少なくなく、優先して水分・電解質補給を開始する必要があります。また栄養状態の確認も欠かせません。長期の食思不振によって体脂肪や筋肉量の減少が懸念される場合もあり、必要に応じて高カロリー輸液や経管栄養を導入することもあります。
原因が特定できれば、その治療を中心に進めていきます。原因がはっきりしないような場合は、まずストレスの軽減に取り組むことが大切です。安心できる環境を整え、愛猫との信頼関係を築くことで、食欲の回復を促していきます。ベッドや食器をいつも通りの場所に置いたり、楽しめる猫グッズをそろえるなど、できる限り日常的な環境やルーティンを保つことが大切です。同時に、食欲増進剤や栄養剤を適宜使用しながら、回復に向けてサポートしていきます。食欲増進剤だけでなく、消化器官の機能改善を促す薬剤を併用することで、食事を摂取しやすい体内環境づくりも重要なポイントです。
3. 考えられる病気
- 猫風邪(猫カリシウイルス、猫ヘルペスウイルス、クラミジア)
- 猫パルボウイルス感染症
- クリプトコッカス症
- トキソプラズマ症
- フィラリア症(犬糸状虫症)
- 甲状腺機能亢進症
- 鼻炎
- 口内炎
- 食道炎
- 巨大食道症(食道拡張症)
- 胃腸炎
- 腸閉塞
- 横隔膜ヘルニア
- 猫伝染性腹膜炎(FIP)
- 膵臓炎
- 糸球体腎炎
- 水腎症
- 慢性腎不全
- 急性腎不全
- 肝炎
- 脂肪肝
- 膵炎
- 尿毒症
- 子宮蓄膿症
- 子宮がん
- 肥満細胞腫
- リンパ腫
- 糖尿病
- 毛球症
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の体重減少には大きく分けて2つの原因があります。1つ目は疾患に伴う代謝異常です。糖尿病や腎疾患、甲状腺機能異常などで基礎代謝量が低下すると、食欲減退や栄養不良を来たし、体重減少を招きます。糖尿病ではインスリン欠乏により糖質代謝異常が生じ、体重減少とともに多飲多尿を来たします。腎疾患では腎機能低下により老廃物の排泄障害から食欲不振を来たします。甲状腺機能異常は代謝機能そのものが低下する疾患で、食欲減退と体重減少を招きます。
2つ目は食事量の減少です。高齢化に伴う食欲低下や歯肉炎等の口内疾患で食事量が減ることで体重減少を来たします。加齢により味覚嗅覚が鈍くなることや、慢性腎臓病等で食欲そのものが低下することが要因です。口内疾患では歯肉炎や歯周病、口内炎等で痛みにより食事摂取が制限されることが多く、結果として栄養不良に陥り体重減少します。
体重減少を訴える猫の特徴として、若齢猫よりも高齢猫に多い傾向にあります。高齢猫は口内疾患等で食事量が減りやすいことに加え、腎機能低下等の老化現象で代謝異常を来たしやすいことが要因です。中高年の猫ほど加齢変化の影響を大きく受け、食欲減退や体重減少が生じやすいといえます。
2. 発見方法と対策
体重減少の兆候を見逃さないためには、体重や体脂肪量を定期的に測定・記録しておくことが有効です。体重は毎日ではなくとも週に一度は計測し、推移をチェックしておきましょう。体脂肪計や体組成計を用いるとさらに正確です。体重減少に気づいたら速やかに獣医師の診断を受ける必要があります。
まず問診や血液検査により代謝異常の有無を確認し、原因疾患の特定に努めます。病歴から食事量の推移も確認します。次に口内の状態を確認し、どれくらい食事を摂取できているか把握します。消化管機能検査等で消化吸収能の評価も行います。これらに基づき体重減少の主因を検討していきます。
原因疾患が特定できればその治療を中心に進めます。不明な場合は食欲減退の原因探索から始めます。口内炎等の有無を確認し、安心できる環境づくりを行いながら食欲増進剤等の投与で食欲回復を図ります。同時に脱水予防のため輸液療法を適宜行いつつ、栄養補給にも取り組み体重減少に歯止めをかけます。経管栄養を選択する場合もあります。体重が大きく減少していれば高カロリー輸液による栄養補給も検討します。
3. 考えられる病気
- フィラリア症(犬糸状虫症)
- 回虫症
- 猫エイズ(猫免疫不全ウイルス:FIV)
- 猫白血病ウイルス(FeLV)
- 口内炎
- 甲状腺機能亢進症
- 食道炎
- 巨大食道症(食道拡張症)
- 胃腸炎
- 腸閉塞
- 巨大結腸症
- 横隔膜ヘルニア
- 猫伝染性腹膜炎(FIP)
- 糸球体腎炎
- 水腎症
- 慢性腎不全
- 肝炎(胆管炎、胆管肝炎、肝硬変)
- 脂肪肝
- 尿毒症
- 肥満細胞腫
- リンパ腫
- 糖尿病
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の体重増加には大きく分けて2つの原因があります。
1つ目は過食です。猫の場合、自発的に運動量を増やすことが難しいため、過剰な食事摂取は体重増加に直結します。飼い主の食事管理や餌選びも強く影響します。
2つ目は疾患関連です。例えば下垂体腫瘍で甲状腺ホルモンが過剰分泌されると代謝亢進を来たし、食欲亢進と体重増加を招きます。インスリン分泌異常でも同様に食欲が増大します。
体重増加しやすい猫の特徴としては、中・高齢の去勢手術後の猫が多い傾向にあります。避妊・去勢手術により基礎代謝量が低下し、運動量も減ることから体重増加が生じやすくなります。近年では子猫も肥満化するケースが増えており、栄養過多な食事内容の長期給餌が影響していると考えられます。
2. 発見方法と対策
体重増加の兆候を見逃さないためには、体重と体脂肪量を定期的に計測して記録することが重要です。計測したデータをもとに体重の推移を確認し、増加傾向を早期にキャッチするようにします。また健康診断時に体重測定を必ず行ってもらいチェックすることも大切です。
体重が増えてきた場合はまず過食の有無を確認します。飼料やおやつの量をしっかりチェックし、次に甲状腺機能異常やインスリン分泌異常などのホルモン疾患の可能性を血液検査で検討します。
原因が特定できればその治療を中心に進めます。原因不明で過食の場合は食事量を調整します。低カロリー食を導入したり運動量を増やすように働きかけます。ホルモン疾患などの場合は薬物治療を選択することもあります。これらによって体重増加を抑制し、標準体重への回復を目指します。
3. 考えられる病気
- 甲状腺機能亢進症
- クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
- 糖尿病
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
便秘は便が硬くなったり、大便の量が減ったりして通常の排便が困難になる状態です。猫の便秘は加齢に伴う肛門括約筋の筋力低下や、食事内容の変化、病気などによって起こります。
中高年の猫ほど便秘になりやすく、10歳を超えた猫では高確率でなんらかの原因による便秘症状がみられます。長毛種のペルシャ猫やメインクーン猫も便秘になりやすい傾向があります。食生活の変化などから一時的に便秘になることもありますが、高齢の猫ほど慢性的な便秘になりやすくなります。
肥満している猫も便秘リスクが高く、運動不足から腸の蠕動運動が低下しやすくなります。また、糖尿病などの病気や腸炎、腫瘍なども便秘の原因となります。ストレスも便秘の誘因となりえます。環境の変化などでストレスが高まると、胃腸の働きが低下して便秘を招くことがあります。
神経障害疾患の場合も便秘の原因となります。椎間板ヘルニアなどの脊椎病変では、神経を圧迫することで腸管の蠕動運動が低下しやすくなります。
薬の服用も便秘の原因となることがあります。鎮痛剤や抗コリン剤、制酸剤などの薬の副作用で便秘を引き起こす可能性があり注意が必要です。
2. 発見方法と対策
便秘の兆候を見逃さないことが大切です。排便の間隔が空く、少量の硬い便を出す、トイレで便秘の様子を見せるが便が出ない、などの症状に気づいたら要注意です。
軽度の便秘なら緩下剤の投与で改善しますが、排便困難が続く場合は浣腸が必要です。高齢猫の便秘には高血圧症状を伴うことが多いので、降圧剤を併用することもあります。
慢性的な便秘になってしまった場合は、食事内容の見直しやプロバイオティクスサプリメント、運動促進などの対策が必要不可欠です。低分子で消化吸収しやすい高品質なフードを選ぶのがおすすめです。
運動不足は改善が必要です。おもちゃを使って遊ばせたり、キャットタワーで遊べる環境を整えることが大切です。ストレスも排除したいところです。環境の変化などが原因の場合、部屋を分けるなどの対策を検討します。空いたダンボール箱を用意するのも安心感を与えられます。
3. 考えられる病気
- 毛球症
- 肝リピドーシス(脂肪肝)
- 巨大結腸症
- 腸閉塞
- 慢性腎不全
- 肛門嚢炎
- 子宮がん
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の下痢は様々な原因で起こりますが、大きく分けて感染性下痢と非感染性下痢があります。
感染性下痢の主な原因はウイルスや細菌、原虫などの感染です。猫パルボウイルスやコロナウイルスなどのウイルス感染は激しい下痢や脱水を引き起こします。一方でサルモネラやカンピロバクターなどの細菌感染では慢性的な下痢になりやすい傾向があります。これらの病原体は糞便を介した経口感染で伝播することが多いため、多頭飼育の場合は感染拡大に注意が必要です。
トキソプラズマ、クリプトスポリジウムなどの原虫感染も下痢の原因となります。これらはネズミや野鳥から感染することがあるので、外出する猫ほどリスクが高まります。
非感染性下痢の原因としては急な餌の変更、ストレス、過敏症、薬の副作用、腫瘍などがあげられます。食生活の乱れやストレスは下痢の誘因となりうるため注意が必要です。
リンパ腫や炎症性腸疾患などで下痢が続く場合もあり、診断のために生検が必要になることもあります。
2. 発見方法と対策
下痢の兆候を見逃さないようにすることが大切です。お尻周りの汚れや臭い、便の色や性状の変化、排便の頻度の増加などに気づいた場合は要注意です。
慢性下痢に対しては糞便検査を行い、原因を特定の上で治療を開始します。ウイルスや細菌感染の場合は抗生物質の投与が中心となります。食事性下痢では原因食品の除去が必須です。ストレス性下痢には環境調整が有効な場合もあります。
下痢が改善しない場合は内視鏡検査や生検を考慮する必要があります。炎症性腸疾患などの可能性もあり、病理結果を踏まえた治療が望まれます。
脱水対策として輸液が必要になることもあります。高齢猫や体の小さな猫ほど脱水しやすい傾向にあるため、体重減少には注意が必要です。
3. 考えられる病気
- 猫エイズ感染症(FIV)
- 猫白血病ウイルス感染症(FeLV)
- 猫パルボウイルス感染症
- 鉤虫症
- 回虫症
- 条虫症
- エキノコックス症(多包条虫症)
- 瓜実条虫症
- トキソプラズマ症
- フィラリア症(犬糸状虫症)
- 甲状腺機能亢進症
- 巨大結腸症
- 胃腸炎
- 横隔膜ヘルニア
- 猫伝染性腹膜炎(FIP)
- 膵臓炎
- 糸球体腎炎
- 水腎症
- 慢性腎不全
- 尿毒症
- 肝炎
- 肝リピドーシス(脂肪肝)
- 膵炎
- 尿毒症
- アミロイドーシス
- 子宮蓄膿症
- 子宮がん
- 肥満細胞腫
- リンパ腫
- 糖尿病
- 熱中症
- 中毒
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
血便の主な原因は胃腸炎、寄生虫感染症、外傷などです。胃腸炎は食事の変更やストレスなどで起き、下痢や嘔吐に血液が混じります。鉤虫等の寄生虫(蠕虫・原虫)が小腸の粘膜を傷つけることでも血便が出ます。交通事故などの外傷では、内臓の損傷により血便を引き起こすことがあります。
血便は子猫や老猫などの抵抗力が弱い個体に多くみられます。免疫力が低下している場合や体調不良な場合に起きやすい傾向があります。症状が重度な場合は早期発見と治療が必要不可欠です。放置すると貧血や脱水症状が進行し、最悪の場合は死に至ることもあるからです。
2. 発見方法と対策
血便の発見には毎日の排便チェックが重要です。赤みや黒みの有無、軟便や下痢の程度、回数の増加などから異常の兆候をつかみます。原因の特定には検便や血液検査等で病原体や炎症反応、腫瘍の有無などを調べます。
治療では対症療法に加え原因治療が必要です。抗生物質、抗がん剤、駆虫薬など、原因に応じた薬を投与します。予防には清潔な環境づくり、ワクチン接種、適切な飼育が大切です。異常が見られたら早急に専門医の診断を受けましょう。状況把握と適切な治療が大事です。
3. 考えられる病気
- 猫パルボウイルス感染症(FPV)
- 鉤虫症
- トキソプラズマ症
- 胃腸炎
- 熱中症
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
泌尿器の症状
1. 原因と傾向
猫の血尿がでる原因には、主に下部尿路疾患(FLUTD)があります。猫の泌尿器にかかわる様々な病気を総称して下部尿路疾患(FLUTD)といいます。
FLUTDの代表的なものとして、膀胱炎や尿石症、尿道炎などがあります。
FLUTDのうち約50%を占めるのが、原因不明の「特発性FLUTD」です。ストレスなどが関与していると考えられています。次に多いのが、食事や体質的な要因による尿石で、FLUTDの約20%を占めます。そのほか、細菌感染によるものもあります。
FLUTDは、若い猫ほど発症しやすい傾向にあります。また、肥満した猫、不適切な食事を与えられている猫、ストレスを受けやすい猫などが罹患しやすいとされています。
特発性FLUTDの原因について、これまでさまざまな仮説が立てられてきました。膀胱上皮のバリア機能異常説や自己免疫説、神経生理学的異常説などがありますが、いまだ決定的な原因は特定されていません。しかし、何らかのストレスが引き金となって発症することが知られています。
肥満はFLUTD再発の危険因子として知られています。過度に高カロリーな食事を与えられたり、運動不足などによって太りすぎることで発症リスクが高まります。逆にカロリーコントロールを意識した食事や適度な運動により適正体重を維持することが再発防止につながります。
2. 発見方法と対策
下部尿路疾患(FLUTD)の代表的な症状は、頻尿、排尿困難、血尿などです。このような症状がある場合は、早めに獣医師の診療を受けることが大切です。
下部尿路疾患(FLUTD)の治療は原因に応じて行われます。急性期の尿路閉塞に対しては緊急カテーテルが行われたり、抗生物質の投与、尿石の除去手術などがおこなわれます。再発しやすい特発性FLUTDに対しては、環境改善によるストレス軽減が有効とされています。
予防には適切な食事、運動、ストレス軽減が重要です。肥満防止、常時清潔な水と食事の提供、猫にストレスの少ない環境づくりに努めましょう。早期発見・早期治療が大切です。
具体的には次のような点に注意しましょう。
・肥満防止のため、適度な運動とカロリーコントロール食を心がける
・常に新鮮な水を用意し、一日に複数回給餌する
・猫のストレス要因を取り除く(他猫とのトラブル、騒音等)
・猫が楽しめる玩具を用意したり、高い場所で過ごせるようにする
・排尿のタイミングや回数の変化に注意する
・尿の色やにおいの変化にも注意を払う
こうした日頃の気配りとともに、1年に一度程度は検診を受けることをおすすめします。異常がなくても尿検査や血液検査を定期的に行うことで、早期発見につながります。
3. 考えられる病気
- 猫下部尿路疾患(FLUTD)
- 猫泌尿器症候群(FUS)
- 膀胱炎
- 熱中症
泌尿器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫のおしっこの色がおかしい原因には、大きく分けて2つのパターンがあります。ひとつは尿路感染症や膀胱炎などによる血尿です。もうひとつは、食事内容や体調の変化に伴う尿の色の変化です。
血尿を引き起こす代表的な病気がFLUTD(猫下部尿路疾患)です。FLUTDには膀胱炎や尿石症、尿道炎などが含まれ、これらが血尿の原因となります。特に肥満した猫やストレスを抱えた猫では発症しやすい傾向にあります。
FLUTDは複雑な病態で、膀胱上皮細胞の変性や炎症、神経生理学的変化など、さまざまな要因が関与していると考えられています。発症のメカニズムの詳細は不明な部分も多いのが現状です。しかしながら、いったん発症すると痛みによるストレスから再発を繰り返しやすいという特徴があります。
一方、食事内容の影響では、アスパラガスやニンニク、玉ねぎなどの食材を食べた後に尿の色が変化することがあります。これは一時的な変化で大きな問題はありません。ただし、赤や黒などに色が変わった場合は血尿の可能性もあるので要注意です。
2. 発見方法と対策
血尿やおしっこの色の変化に気づいたらまず獣医師の診断が必要です。検尿や画像検査により、血尿の有無やその原因を特定します。
治療は原因疾患に対して行われます。抗生物質投与、尿石除去、食事指導などがおこなわれます。予防には過度なストレスを避け、バランスのとれた食事を心がけることが大切です。
具体的には、ストレス要因の特定や尿酸値・pHの測定、定期検査の実施などが挙げられます。日常生活のなかでも、おしっこの量や頻度、色の変化などに常に気を配ることが再発防止につながります。
3. 考えられる病気
- 肝炎(胆管炎、胆管肝炎、肝硬変)
- 膀胱炎
- 中毒
泌尿器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫のおしっこの量が増える症状の原因には大きく分けて2つのパターンがあります。ひとつは腎臓の機能低下によるもので、もうひとつは体内の抗利尿ホルモン分泌量の低下によるものです。
前者の腎機能低下は、腎臓そのものの疾患や腎臓以外の疾病に起因することがあります。腎臓そのものの疾患としては慢性腎臓病や腎炎、腎臓の腫瘍などが代表的です。こうした疾患では腎臓の働きをつかさどる糸球体や尿細管に何らかの障害が生じ、老廃物のろ過や水分の再吸収が十分にできなくなります。その結果、余分な水分を体外に排出しようとしておしっこの量が増えるようになります。
腎臓以外の疾病に起因する腎機能低下としては、心臓病、肝臓病、膵臓病、ホルモン異常症などが関係している場合があります。これらの疾患では体内環境の変化により腎臓への血流量が低下したり、老廃物の排出に必要なホルモン分泌が低下するなど、結果的に腎機能が低下し多飲多尿状態となります。
後者の抗利尿ホルモン分泌量の低下は、脳下垂体や甲状腺のホルモン異常、脳疾患、中枢神経系への損傷などが原因となります。抗利尿ホルモンは体内の水分バランスを正常に保つ上で大切な役割を果たしています。分泌量が低下することで水分排出量の調整に障害が生じ、結果多飲多尿となります。
これらのうち、高齢の猫ほど腎機能低下に起因する多飲多尿が起こりやすく、症状の程度も年齢とともに進行する傾向が顕著です。ただし、若年で腎臓そのものの疾患等に罹患した場合も珍しくなく、さらに遺伝的な要因も関係していると考えられています。
2. 発見方法と対策
多飲多尿の症状は、飼い主が普段の猫の生活パターンを理解していれば、比較的早期に気づくことができます。具体的には、以前よりも水やおしっこの量が増えたと感じたり、トイレの利用頻度が高くなったことに気づいた場合等です。
この症状が見られた場合は速やかに獣医師の診療を受けることが大切です。診断のためには血液検査や尿検査を行い、腎機能の状態やホルモン値を確認します。検査結果に応じて、腎機能改善のための薬物治療や食事療法を行ったり、ホルモン補充療法等の対処をします。
治療と並行して、多飲多尿を引き起こす水分摂取量の調整も重要です。水分制限をする一方で脱水に注意し、適度な水分補給を心がけます。
早期発見と適切な治療によって症状の進行を防ぐことが可能です。予防策としては定期的な検診による健康チェックを心がけることがあげられます。若年時からのフォローも欠かせません。
3. 考えられる病気
- 猫白血病ウイルス(FeLV)感染症
- 甲状腺機能亢進症
- 肝炎(胆管炎、胆管肝炎、肝硬変)
- クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
- 糸球体腎炎
- 慢性腎不全
- 子宮蓄膿症
- アミロイドーシス
- 糖尿病
泌尿器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫のおしっこの量が減る症状の主な原因は、腎臓や膀胱、尿道などの尿路に関する疾患です。
代表的なものとして、膀胱炎や腎炎、尿結石による尿道の閉塞などがあります。こうした疾患では、膀胱や尿道への炎症や障害、あるいは腎臓の老廃物ろ過機能の低下などにより、排尿量が減少します。
中でも尿道の物理的な閉塞は重篤で、治療が遅れると急速に腎不全を招きます。他にも腎臓癌などの腫瘍性疾患、先天性の腎臓異常、心不全や肝硬変などほかの臓器の疾患による二次的な腎機能低下なども考えられます。
尿道の閉塞は、尿結石や炎症に伴うものが主な原因となります。この状態が長引くと腎臓から膀胱への尿の流れが妨げられ、排尿量の減少につながります。また閉塞が完全なものであれば膀胱内圧が異常に上昇し、腎機能障害や尿漏れを招くこともあります。
腎臓自体の機能低下は、腎実質の炎症や癌によるダメージなどに起因します。糸球体や尿細管が障害されることで老廃物のろ過や水分再吸収が不全となり、排尿量の減少を招きます。
ほとんどが中高年以上の猫で発生しますが、比較的若齢の猫でも腎臓疾患などで起こることがあります。
2. 発見方法と対策
おしっこの量の減少は日常生活の中で気付きにくい症状の一つです。トイレの利用頻度やおしっこの量を常日頃からチェックしておくことが大切です。
気付いた際には速やかに専門医の検査を受けましょう。血液検査やエコー、X線撮影などで腎臓や下部尿路の状態を評価し、適切な治療を開始します。
治療法は原因疾患に対応したものとなりますが、患部の炎症を抑えつつ腎機能低下を防ぐことを目標とします。膀胱や尿道のpH調整、抗生物質の使用、利尿薬の投与などが行われます。可能な限り保存的治療を先行しますが、手術を要する場合もあります。
予防には定期検査による早期発見と、過度な食事・運動・ストレスを避けた生活環境の調整が有効です。適度な水分摂取を促し、腎臓負担の軽減にもつながります。
早期発見、早期治療を心掛けることで腎機能の悪化を防ぎ、健康寿命の延伸が可能です。
3. 考えられる病気
- 猫下部尿路疾患(FLUTD)
- 猫泌尿器症候群(FUS)
- 膀胱炎
- 急性腎不全
泌尿器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
四肢(手足)・関節の症状
1. 原因と傾向
猫の歩き方がおかしい、つまり歩行異常を示す場合、その原因としてはさまざまな病気が考えられます。
代表的なものとしては、脊椎症や四肢の外傷・骨折、ビタミンB1欠乏症、中毒などがあります。これらの病気は、猫の神経系や骨・関節・筋肉など運動器系に影響を及ぼし、歩行時の平衡感覚や運動能力を低下させることで、歩き方の異常をもたらします。
具体的には、脊椎症では脊柱の変形や脊髄への圧迫により後肢の麻痺などを引き起こし、四肢の外傷や骨折では痛みや支持力の低下から歩行困難を招きます。
生のイカや貝などの魚介類や、カニ、エビなどの甲殻類はビタミンB1を分解する酵素を持っているため、猫に与えると体内のビタミンB1が欠乏してビタミンB1欠乏症となり、運動失調や麻痺を引き起こすことがあります。魚介類は必す加熱調理をして与えるようにしましよう。
年齢的には、高齢猫ほど歩行異常が起こりやすい傾向にあります。加齢に伴う関節の変形性疾患や筋力低下が影響していると考えられています。
また、後天的な外傷や病気に対する回復力が低下していることも、歩行異常のリスクを高める要因の一つです。免疫機能の低下や代謝機能の鈍化が、外傷後の治癒過程や疾病からの回復を遅らせ、歩行障害が長期化・永続化することにつながります。
このほかにも、肥満に伴う関節への負担増が歩行異常の誘因となることが知られています。運動量の減少や過食が原因で急速に体重が増えた場合、関節や靭帯への過度の負荷がかかり、変形性関節疾患などを引き起こします。
2. 発見方法と対策
猫の歩行異常の兆候を見逃さないよう、日頃から様子をよく観察することが大切です。
具体的には、猫が立ち上がる際に体のバランスを取れずによろめいたり、歩く速度が遅くなったり、歩幅が狭くなったり、脚を引きずるようになったりする様子に注意しましょう。
こうした兆候が見られた場合には、速やかに獣医師の診断を受けることをおすすめします。獣医師が原因疾患の特定や必要な検査・治療を行うことで、症状の進行を防ぎ、猫の生活の質を守ることができます。
具体的な検査としては、エックス線やCT、MRIなどの画像検査のほか、血液検査や尿検査、関節液検査などを行い、歩行異常の原因を特定します。例えば血液検査からビタミンB1欠乏が判明したり、画像検査で脊椎の変形が確認できたりすることで、的確な治療方針を立てることができます。
治療としては、原因となっている病気に対する薬物療法や、外科的治療が行われます。薬物療法では痛み止めなどの鎮痛薬・抗炎症薬やビタミン剤などを投与し、外科的治療では骨折・湾曲部の固定・矯正などを行います。
また日頃から、運動不足やストレスが蓄積しないよう環境を整え、バランスの良い食事を与えるなど、猫の健康管理に気を配ることも大切です。特に老齢猫の場合は歩行機能低下に対するリハビリテーションが有効であることが知られているので、継続的なリハビリを行うことをおすすめします。
3. 考えられる病気
- クリプトコッカス症
- ビタミンB1欠乏症
- 中耳炎
- 骨折
- 変形性関節症
- 糖尿病
- 中毒
四肢(手足)・関節の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫が動くのを嫌がる主な原因としては、骨・関節疾患、外傷・骨折、神経疾患、感染症などがあげられます。これらの病気では、動くことによる痛みや違和感が生じるため、日常的な動きを控えがちになります。
変形性関節症では関節の変形や軟骨の磨耗で動くたびに痛みが生じ、四肢への外傷や骨折では明らかな痛みと支持力の低下が起きます。ほかにも糖尿病性神経障害、腰痛症、癌などでも疼痛を伴うことがあります。
高齢の猫で多く認められ、加齢に伴う関節の変形と痛覚の鈍化が影響していると考えられます。太りすぎている肥満猫でも関節への負担が大きくなるため、動くのを好まないケースがよく見受けられます。
2. 発見方法と対策
日頃から猫の様子や動きを注意深く観察し、動くことを避けている傾向が強まれば要注意です。獣医師による診断で原因疾患の特定と治療が必要です。
治療としては、変形性関節疾患なら鎮痛薬・抗炎症薬やサプリメントの投与、骨折なら整復とギプス固定が行われます。リハビリテーションも併用されることが多く、徐々に動かす習慣をつけさせます。
予防には過度な肥満防止、ストレス解消、十分な運動確保など、猫の健康管理が大切です。高齢猫は体力の低下を見極め、無理のない範囲で日常動作を促します。
3. 考えられる病気
- ヘモバルトネラ症(猫伝染性貧血)
- 心筋症
- 骨折
- 変形性関節症
- 横隔膜ヘルニア
- 膵炎
- 脂肪織炎
四肢(手足)・関節の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の肉球が腫れる主な原因は、形質細胞性足底皮膚炎、アレルギー性皮膚炎、外傷・火傷などです。これらの病気では、免疫異常反応や物理的な炎症刺激で肉球部位に炎症が起こり、腫れが生じます。
形質細胞性足底皮膚炎では自身の正常組織を異物と判断する自己免疫反応が関与していると考えられていますが、はっきりとした原因はわかっていません。アレルギー性皮膚炎もアレルゲンに対する免疫の異常反応です。
外傷・火傷では物理的刺激としての組織損傷が主原因ですが、治癒過程で過剰に炎症反応が起こることもありえます。
老齢ほど発生しやすい傾向にあり、加齢に伴う免疫機能低下が影響している可能性が考えられます。痛覚が鈍化していても異常は進行するため、高齢猫ほど肉球の腫れに注意が必要です。
2. 発見方法と対策
肉球の腫れは日常のブラッシングやトリミング時などに両側対称性に確認できます。獣医師の検査で原因疾患を特定した上で、ステロイド薬や抗生物質、保湿剤などを使用して治療します。外傷性の場合は湿潤療法も併用されます。
予防には清潔保持、過度な肥満防止、アレルゲンの接触抑制など日頃の管理が有効です。高齢猫では肉球の日常の確認を怠らないことが大切だと言えます。
3. 考えられる病気
- アレルギー性皮膚炎
- 形質細胞性足皮膚炎
- 外傷
- 火傷
四肢(手足)・関節の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
猫の関節の腫れには、大きく分けて外傷性と非外傷性のものがあります。
外傷性の代表例は、交通事故や高所からの転落などによる打撲や捻挫、脱臼、骨折です。こうした外力による強い衝撃で関節にダメージを受け、腫れや痛みを引き起こします。特に骨折を伴う場合、関節くるみは著しく腫れあがります。骨折部位が適切に固定されないと、更なる関節の変形を招きます。
一方で非外傷性の関節の腫れとしては、感染症や炎症、変形性関節症、腫瘍などがあります。例えば関節炎では、関節包を含む軟部組織の炎症腫脹を起こします。免疫介在性疾患のひとつである関節リウマチでも、自己抗体の関節への沈着によって炎症が持続して肥厚化が起こり関節はむくんでくるようになります。
腫瘍による関節の腫れもあり得ます。例えば骨肉腫は骨組織を主座とする悪性腫瘍で、関節近傍での発生は稀ですが、発生すれば骨組織の破壊とともに著明な腫脹を引き起こします。
ほかには、過度の運動や肥満による体重負荷も原因の一つです。特に肥満時は体重が関節にかかる圧力を増大させるため、変形性関節症の誘因となりえます。
いずれにせよ、関節の腫れは疼痛の原因となり、関節の可動域制限や変形を引き起こす可能性があります。放置すれば腫れはさらにひどくなる一方で、適切な治療によって改善できる場合が多いため、早期発見と対応が大切です。
2. 発見方法と対策
関節の腫れの兆候として、まず歩き方の変化に気づくことが多いでしょう。腫れた関節を庇おうとして歩いたり、痛みを避けるために体重をかけないようにするからです。
次に、腫れている関節部位をなるべく動かそうとしないこともポイントです。猫が腫れた関節を使おうとせず、そっけない様子を示すのは異変の表れと考えられます。
実際に触診すると、当然のことながら関節部位の熱感や腫脹、圧痛を確認できるはずです。X線やMRI、CTなどの画像検査を行えば、さらに詳細な腫れの状態、原因となる疾患の特定につながる情報が得られるでしょう。
例えば変形性関節症では関節軟骨や骨の変化が、リウマチ性疾患では特有の関節液の増加や滑膜の肥厚がそれぞれ確認できます。
対処としては、まず外傷性の腫れであれば、骨折などの場合には整復固定や手術による治療が必要不可欠です。リハビリテーションによる機能回復にも力を入れるべきでしょう。抗生物質の投与による感染症のコントロールも重要です。
非外傷性の腫れの治療法は原因疾患によって異なりますが、関節リウマチなどの炎症性疾患ではステロイド薬や免疫抑制剤、鎮痛剤などを用います。変形性関節症の進行には関節の固定なども考えられます。
早期発見と適切な治療が大切です。放置すれば更なる腫れや変形の進行で、猫の健康と生活の質は低下していきます。予防には食事と運動のバランス改善、室内飼いを基本とすることが重要だと考えます。
3. 考えられる病気
- 骨折
- 脱臼
- 変形性関節症
- 関節リウマチ
- 悪性腫瘍
四肢(手足)・関節の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
本ページには細心の注意を払ってコンテンツを掲載していますが、その正確性、安全性、有用性等について、お客さまに対し、何ら保証するものではありません。コンテンツのご利用により、直接または間接であるかを問わず、万が一何らかの問題、損害・損失が発生した場合でも、弊社は一切の責任を負いかねます。コンテンツのご閲覧・ご利用等にあたっては、お客さまご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。