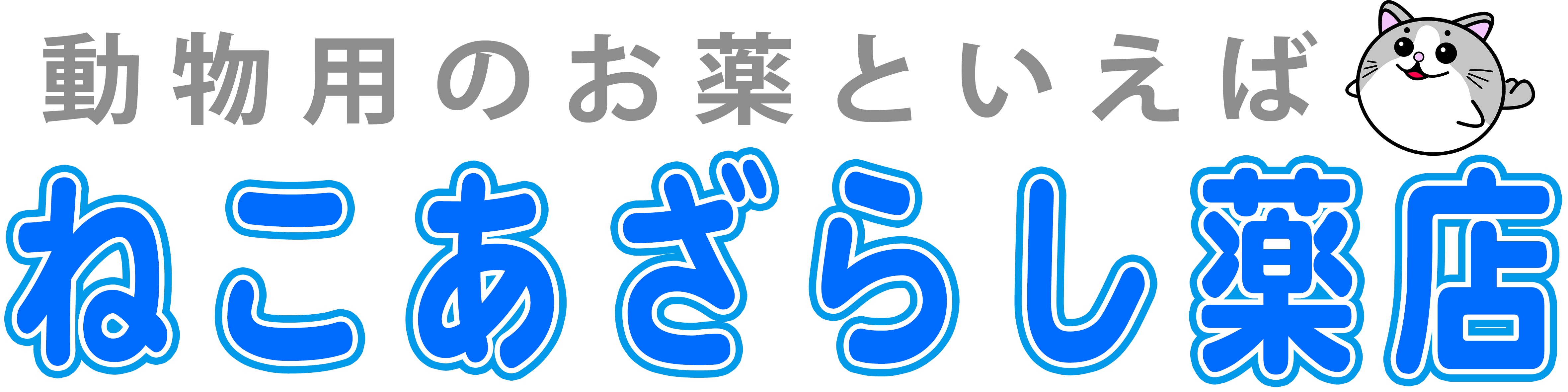目の症状
1. 原因と傾向
めやに・涙の両方が出やすくなっている場合、眼球内の炎症やブドウ膜炎・眼瞼外反症・眼瞼内反症などの可能性があります。いつも涙が出ている場合は涙管閉塞の可能性が高く、目の涙やけをおこすこともあります。
2. 発見方法と対策
普段から、目の周囲の汚れや様子をチェックすることで症状に気付くことができます。特に、涙やけや、目の充血には注意が必要です。また、前足で目をこする仕草をしたり、瞬きの回数が異常に多いなど、普段の様子との違いから発見することもできます。
外的要因は、こまめに毛のブラッシングをしたり、シャンプーの際は目を避けるなどで対策することが可能です。
また、眼科用の薬剤による治療も行われ、炎症や感染を抑えます。
3. 考えられる病気
- 結膜炎
- 角膜炎
- ブドウ膜炎
- 眼瞼内反症
- 眼瞼外反症
- 流涙症
- 逆さまつ毛
- 犬ジステンパーウイルス感染症
目の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の目が白く濁る主な原因として、緑内障、角膜炎、白内障があげられます。
緑内障は眼の房水の流れが障害され、眼圧が上昇することで起こります。急性期には眼の強い充血や角膜の青灰色の混濁が見られ、頭を触るのを嫌がったり嘔吐したりすることもあります。シーズーなどの犬種に多く、放置すると視力喪失の危険があります。
角膜炎は目の物理的・化学的刺激やウイルス感染などにより角膜に炎症が起こる疾患です。光を嫌がったり、目の充血や白濁が進むと痛みも強くなります。
白内障は水晶体の濁りによって視力が低下する病気で、歩行時のぶつかりなどで気付くことが多いのですが、飼い主の発見が遅れがちです。犬では加齢に伴うものが一般的です。
2. 発見方法と対策
緑内障や角膜炎では、日頃から目の状態に気を配り、充血や白濁などの異常がないか確認することが重要です。光を嫌がったり、目をこする行動も症状のサインとなります。
白内障の場合は、視力低下に伴う歩行の異常などの行動の変化に注意が必要です。いずれも早期発見が予後の改善につながるため、定期検査を受けることも勧められます。
治療は、点眼薬や手術など病状に応じて行われます。注意深い観察による早期発見、獣医師の指示に基づく適切な治療が大切です。予防には清潔な環境やストレス軽減など日頃の管理に加え、定期検査の受診が推奨されます。
3. 考えられる病気
- 緑内障
- 角膜炎
- 白内障
目の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の目が赤くなる主な原因は、結膜炎や角膜炎、チェリーアイなどの眼の疾患です。
結膜炎は結膜の炎症により、目の充血、やに、涙などの症状が起こります。細菌、ウイルス、アレルギーなどさまざまな要因が考えられます。
角膜炎は角膜に炎症が生じ、目の痛みや白濁を招きます。物理的な刺激や感染症が原因となります。
チェリーアイは、目の裏側にある腺組織が飛び出して赤く腫れる病気です。若い犬に多く、外傷や腫瘍なども原因となります。これらの病気では、目の充血や異常が特徴的な症状となります。
2. 発見方法と対策
日頃から犬の目の状態に注意し、充血や赤み、分泌物の有無を確認することが大切です。また、目をこする行動の変化なども重要なサインです。これらの目の疾患は、放置すると重篤化する可能性があります。異常が見られた場合は早期に獣医師の診断を受ける必要があります。
治療法としては、点眼薬の使用や原因となる疾患の治療などが行われます。感染症対策や清潔な環境の維持なども予防には重要です。飼い主の注意深い観察と、獣医師の適切な治療により、目の健康を守ることができます。
3. 考えられる病気
- 結膜炎
- 角膜炎
- チェリーアイ(第三眼瞼腺逸脱)
目の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
鼻の症状
1. 原因と傾向
犬の鼻水やくしゃみの主な原因疾患として、鼻炎、副鼻腔炎、クリプトコッカス症等があります。
鼻炎はウイルスや細菌、カビ等の感染により鼻腔の粘膜が炎症を起こし、水様あるいは膿性の鼻汁とくしゃみといった症状を引き起こします。鼻炎が未治療の状態が長引くと、副鼻腔への波及によって副鼻腔炎を併発することがあります。
副鼻腔炎では、濃い鼻汁や鼻血が特徴的な症状となります。
一方、クリプトコッカス症はカビの一種であるクリプトコッカスによって引き起こされる呼吸器感染症で、鼻水とくしゃみが主症状ですが、カビが肺や中枢神経にまで感染すると呼吸困難や神経症状を呈する可能性があります。
これらの疾患は放置すれば重症化しやすく、飼い主の注意深い観察と早期発見、獣医師による適切な治療が必要不可欠です。
2. 発見方法と対策
鼻水やくしゃみに加え、鼻血、口呼吸、頭部の腫れなどの症状にも注目する必要があります。
鼻炎から副鼻腔炎やクリプトコッカス症への移行を防ぐためには、鼻炎の初期症状に対する早期治療が重要です。獣医師の診断に基づいて、抗生物質、抗真菌薬、抗炎症薬等の内服薬による薬物療法が行われます。必要に応じて鼻腔洗浄や手術等の外科的治療も選択されます。原因がアレルギーであれば除去療法も有効です。空気清浄器の使用や散歩時のマスク装着も対策の一つです。ワクチン接種による予防も大切です。
3. 考えられる病気
- 鼻炎
- 副鼻腔炎
- クリプトコッカス症
- ジステンパーウイルス感染症
- 肺水腫
- 犬伝染性肝炎
鼻の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
口の症状
1. 原因と傾向
犬の口臭の主な原因は、歯周病、尿毒症、虫歯、口内炎などの口腔内や全身の疾患です。
歯周病では歯と歯肉の間に炎症が起こり、口臭のほか出血や歯のゆるみなどをもたらします。尿毒症は腎臓の機能低下により老廃物が蓄積し、時にアンモニア臭の口臭が生じます。
虫歯は歯垢中の細菌により歯が溶けて穴があき、口臭の原因となります。
口内炎はウイルスや細菌感染などにより口腔内に炎症が起こり、強い口臭を引き起こします。
これらの疾患は放置すれば全身状態の悪化や重篤な合併症を招きます。
2. 発見方法と対策
普段から口の中の臭いや歯肉出血、食事量の変化などに注意し、異常があれば早期に獣医師の診断を受けることが大切です。
歯周病では歯の洗浄と抜歯、尿毒症では透析による老廃物の除去、虫歯では詰め物や抜歯による治療が行われます。口内炎では原因疾患の治療とともに、口腔の清潔保持が重要です。
予防には歯磨きの習慣づけ、適切な食事、腎臓病の早期発見などが挙げられます。
飼い主の継続的な健康管理と観察、獣医師との緊密な関係が口臭をはじめとする疾患の予防、早期発見、適切な治療につながります。
3. 考えられる病気
- 歯周病
- 虫歯
- 口内炎
- 尿毒症
- 口腔内悪性黒色腫(メラノーマ)
- 下痢
口の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の口の中の出血の原因としては、歯周病、レプトスピラ症、悪性黒色腫、扁平上皮がんなどがあります。
歯周病では歯と歯肉の間に炎症が起こり、出血することがあります。
レプトスピラ症はレプトスピラ菌の感染により黄疸型では口内出血が見られます。
悪性黒色腫では口腔内の腫瘍形成により出血が起こります。
扁平上皮がんも口腔内腫瘍による出血を引き起こします。
これらの病気は放置すると重症化あるいは転移のリスクがあるため、出血などの症状には早急な対応が必要です。
2. 発見方法と対策
普段から口の中の異常に気を配り、出血があれば速やかに獣医師の診察を受けることが大切です。
歯周病では治療として歯石の除去や抜歯が、レプトスピラ症では抗生物質の投与が行われます。
悪性黒色腫や扁平上皮がんでは外科的切除や化学療法が主治療となります。
定期的な口腔内のチェックによる早期発見が予後の改善につながります。歯垢の除去など口腔内の清潔保持が予防には効果的です。飼い主の継続的な健康観察と、獣医師の適切な治療が欠かせません。
3. 考えられる病気
- 歯周病
- レプトスピラ症
- 口腔内悪性黒色腫(メラノーマ)
- 扁平上皮がん
口の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の口内炎の主な原因は、ウイルスや細菌、カビなどの感染症、外傷、重度の歯周病、全身疾患などがあります。感染症ではジステンパーウイルスやレプトスピラ菌などが関与します。異物による外傷でも口内炎は起こりえます。歯周病が重度の場合、口内炎を併発しやすくなります。全身疾患としては糖尿病や自己免疫疾患などで口内炎がみられることがあります。栄養状態の悪化や免疫力の低下もリスクを高めます。痛みや出血、口臭などを伴うため、口内炎の早期発見と治療が必要不可欠です。
2. 発見方法と対策
口の中の赤み、ただれ、出血などの症状に注意が必要です。原因疾患があればその治療に加え、抗生物質や抗炎症薬などの投与が行われます。口腔内の清潔保持が重要で、歯周病などの治療や抜歯も選択されることがあります。栄養管理の改善も重要な対策といえます。
予防には常時の歯みがきと口腔内の清潔保持が効果的です。また全身疾患の早期発見・早期治療も欠かせません。飼い主の継続的な健康管理と観察、および獣医師の適切な治療が口内炎の予防と改善につながります。
3. 考えられる病気
- 口内炎
- 口腔内悪性黒色腫(メラノーマ)
- 扁平上皮がん
口の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬のよだれが増量する代表的な原因疾患として、てんかん、熱中症、肝性脳症を伴う門脈シャント、狂犬病、口内炎、胃捻転症などが挙げられます。
てんかん発作の前兆症状として、よだれが増えることがあるでしょう。熱中症では体温上昇に伴い、汗をかくことのできない犬は唾液分泌を増加させるため、よだれが増えます。門脈シャントでは肝機能障害によりよだれが見られることがあります。狂犬病の前駆期にもよだれの増量が認められます。口内炎では疼痛により血液混入のよだれを伴うことがあります。胃捻転では嘔吐不能のためよだれが貯留します。
いずれも放置すれば重篤化する疾患群ですので、よだれ量の変化に注意が必要です。
2. 発見方法と対策
日頃から犬のよだれ量に注意し、異常な増加が認められた場合には速やかに獣医療診療を受けることをお勧めします。
てんかんでは抗けいれん薬の投与、熱中症では冷却法、狂犬病予防にはワクチンが有効です。口内炎では原因治療と口腔清潔が必要となります。胃捻転では早期の整復手術が必須です。予防策として過度の運動や高温環境の回避、ワクチン接種、口腔衛生の維持などが重要です。
飼い主様と獣医師が連携し、疾患の早期発見と適切な治療に努めることが大切です。
3. 考えられる病気
- 口内炎
- 胃拡張・胃捻転症候群
- 熱中症(熱射病、日射病)
- 口腔内悪性黒色腫(メラノーマ)
- 門脈シャント
- 狂犬病
- てんかん
口の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
歯の症状
1. 原因と傾向
犬の歯が茶褐色や灰褐色、黒色に変色する代表的な原因は虫歯です。
歯垢中の細菌によって生成した酸が、歯の表面を侵食することで虫歯が発生します。症状の初期段階では自覚症状はほとんどありませんが、虫歯が進行するにつれて疼痛や口臭を伴うようになります。
犬の場合、犬歯や上顎臼歯の深い溝に生じることが多い傾向にあるようです。早期発見と適切な治療が大切です。
2. 発見方法と対策
歯の変色には日ごろから注意を払う必要があります。変色を認めた場合は速やかに獣医師の診断を受けることをお勧めします。
治療としては病変部の削開と充填などが行われます。予防には日常の歯垢コントロールと定期検診が効果的と考えられます。虫歯の早期発見と適切な対応により、重症化を防ぐことが大切です。
3. 考えられる病気
- 虫歯
歯の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
歯石は歯垢が石灰化したものです。歯垢が放置されると歯石が形成され、その表面にさらに歯垢が付着する悪循環となります。
歯肉の炎症、出血、口臭などを引き起こす歯周病の主な原因となります。歯石がたまりやすいのは歯と歯の間で、ブラッシングが行き届きにくい箇所です。年齢とともに歯石は増えていきます。
2. 発見方法と対策
歯肉の異常や口臭などから歯石の蓄積を疑うことができます。歯科検診時に歯石の有無を確認することも大切です。
治療には麻酔下での歯石除去が行われます。予防には幼齢期からのブラッシングが効果的です。適切な口腔ケアで歯周病の発症を防ぎましょう。
3. 考えられる病気
- 歯周病
- 虫歯
歯の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
耳の症状
1. 原因と傾向
犬が耳をかく主な原因として、耳ダニ感染症と外耳炎があります。
耳ダニ感染症は耳ダニの寄生により起こり、耳の中に黒い耳垢が蓄積するほか、耳ダニによる刺激で強いかゆみを感じてしきりに耳をかいたり頭を振ったりします。外耳炎は細菌や真菌などの感染によって外耳道の炎症を引き起こし、耳の痛みやかゆみによって耳をかく行動が見られます。
いずれも放置すると炎症が広がったり再発を繰り返したりして治りにくくなる傾向があるため、早期発見と適切な治療が大切です。飼い主の注意深い観察が必要不可欠といえます。
2. 発見方法と対策
耳のかきむしりや頭の振りに加え、耳の赤み、腫れ、異臭などの症状にも注意が必要です。
治療には原因となる耳ダニや細菌、真菌の駆除が重要で、耳垢の除去、殺虫剤、抗生物質、抗真菌薬の使用など、適切な対応が取られます。再発を防ぐには原因となる疾患のコントロールが欠かせません。
予防策としては、耳の清潔保持と定期的な耳状態のチェックがあげられます。
飼い主の観察力と獣医師との緊密な関係が、症状の早期発見、適切な治療につながります。
3. 考えられる病気
- 外耳炎
- 耳ダニ感染症
- 耳血腫
耳の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の耳垢が多い症状の主な原因としては、外耳炎と耳ダニ感染症の2つが挙げられます。
外耳炎は、耳の中の細菌や真菌が異常増殖することで起こります。炎症により耳垢の分泌が増え、黒くてベトベトした耳垢がたまりやすくなります。特に垂れ耳の犬種が罹患しやすい傾向にあり、アレルギー体質の犬も発症リスクが高い特徴があります。放置すると耳道の狭窄や聴覚障害につながる可能性もあるため、早期発見と治療が大切です。
一方、耳ダニ感染症は、耳の中に寄生するダニ類「ミミヒゼンダニ」によって発症します。ミミヒゼンダニは耳の中で増殖しながら犬の組織液を吸収するため、耳の中に黒い耳垢がたまったり、耳が強く痒くなったりします。垂れ耳の犬種に多くみられ、放置すると外耳炎などを併発する可能性が高いのが特徴です。早期発見と治療が大切な疾患といえます。
2. 発見方法と対策
外耳炎における耳垢の増加の発見方法は、耳の中をのぞき込んで黒くてベトベトした耳垢の量や性状を確認することです。治療には耳洗浄と抗生物質や抗真菌薬の使用が必要不可欠です。根気強い治療が必要となりますが、原因を特定して対処することが大切です。
一方、耳ダニ感染症の発見も耳の中の観察が基本です。黒い耳垢の蓄積に加え、耳を振ったりかいたりする症状にも要注意です。治療には耳垢の除去と殺ダニ剤の投与が必要です。他のペットとの接触も制限し、同居動物の治療も必要に応じて行うことが大切です。
いずれの疾患も定期的な耳のチェックが予防の基本となります。異常が見つかったら獣医師の診断を速やかに受け、適切な治療を開始することが大切です。
3. 考えられる病気
- 外耳炎
- 耳ダニ感染症
耳の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の耳が膨らむ症状の主な原因として耳血腫が挙げられます。
耳血腫は耳の内部に血液や分泌液がたまることで起こり、耳介全体が赤く腫れ上がる症状です。
耳血腫の発生要因には、外耳炎などによる耳のかゆみや痛みで耳をかくことが関係していると考えられています。また、耳を強く打撲したり、他の犬に噛まれたりした外傷が原因になるケースもあります。発症しやすい犬種などの傾向は明らかではありません。
放置すると耳の軟骨が変形し、形状が崩れることもあるため、早期発見と治療が重要です。
2. 発見方法と対策
耳血腫の発見は、耳の膨らみや赤み、熱っぽさの確認が基本です。軽度の場合は小さな膨らみだけで気づきにくいこともありますので、耳の観察は丁寧に行う必要があります。
治療では吸引や切開により液を排出した後、抗生物質などの投薬で感染予防を行います。再発防止には原因となる耳の病気の治療が重要です。
予防法としては、外傷を避けること以外に特別な対策はありませんが、耳の健康管理を心がけることが大切です。
3. 考えられる病気
- 耳血種
耳の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の耳が聞こえづらい症状の主な原因は、内耳炎、中耳炎、外耳炎などの耳の疾患です。
内耳炎は中耳炎や外耳炎からの波及により起こり、バランス障害や傾斜などの症状が現れます。中高年の犬に多く、放置すると難聴につながります。
中耳炎は細菌感染などにより中耳に炎症が起こる疾患で、顔面麻痺などの神経症状を引き起こします。
外耳炎も細菌感染などで外耳道に炎症が起こる疾患で、耳のかゆみや耳垢の増加などを招きます。
いずれも慢性化しやすく、放置すれば重度の難聴に陥る可能性があるため、早期発見と治療が必要です。
2. 発見方法と対策
聞こえづらさの自覚は困難なので、呼びかけに反応しないなどの異変に注目します。傾斜や耳振りも要チェックです。
治療は原因となる炎症の鎮静化を図ることが基本。抗生物質や抗炎症薬の使用とともに、根気強い耳の手入れが必要不可欠です。
予防には清潔な耳の維持が大切です。さらに早期発見のため、定期的な検査を心がけることをおすすめします。
3. 考えられる病気
- 内耳炎
- 中耳炎
- 外耳炎
- 認知症
耳の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
皮膚の症状
1. 原因と傾向
犬の皮膚が荒れる症状の主な原因は、細菌感染による膿皮症、ノミやダニ類の寄生、アレルギー性皮膚疾患などです。
膿皮症はブドウ球菌などの細菌感染で起き、膿疱や発疹などの症状が現れます。短頭種やシェパード種に多くみられる傾向があり、首周りや顔面、脇の下、尾周りなどに発症しやすい特徴があります。不衛生な飼育環境がリスク因子となるため、清潔な環境を保つことが予防に重要です。膿皮症はアレルギー性皮膚疾患などを基礎に発症することもあるため、基礎疾患の治療も合わせて行う必要があります。
ノミ・ダニによるアレルギー性皮膚炎はノミに刺されることで免疫反応が起こり、発症します。痒みと脱毛が特徴的で、背中から尾の付け根にかけての部位に多くみられます。アレルギー体質の犬や若齢犬が罹患しやすく、寄生虫であるノミの完全駆除が治療のカギとなります。家庭環境の消毒も重要で、再感染を防ぐためには継続的な駆除が必要不可欠です。
アトピー性皮膚炎もアレルギー反応が原因で、かゆみと炎症を主症状とします。若齢犬に多く発症し、原因抗原の特定が難しいのが特徴です。環境抗原への曝露を減らすことや皮膚の保湿ケアが治療方針の基本となります。
いずれも放置すれば重症化の恐れがあるため、早期発見と適切な治療が必要不可欠です。
2. 発見方法と対策
皮膚の赤み、痒み、脱毛などの兆候に注意します。部位の広がり方などから原因をある程度推定できます。例えば、短頭種の顔面に膿疱がある場合は膿皮症の可能性が高いでしょう。背中の脱毛と痒みはノミ・ダニアレルギーを疑う材料となります。
治療は原因となる疾患に対応した薬物療法が基本となります。細菌感染であれば抗生物質の使用。ノミ・ダニがみられたら駆除薬の使用が適切です。炎症を抑える副腎皮質ステロイド薬の併用も一般的です。
予防には清潔な環境と栄養バランスの維持が非常に重要です。定期的な皮膚チェックや異変時の早期受診も予防に効果があります。健康な皮膚を保つことが皮膚疾患の発生予防につながります。
3. 考えられる病気
- ノミアレルギー性皮膚炎
- アトピー性皮膚炎
- 膿皮症
- 疥癬
- アカラス症(ニキビダニ症、毛包虫症)
- 脱毛症
- 肥満細胞腫
- 扁平上皮がん
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の皮膚に発疹ができる原因としては、アレルギー反応によるアトピー性皮膚炎や食物アレルギー、ノミ・ダニアレルギー、細菌や真菌感染症などが挙げられます。
アトピー性皮膚炎では、アレルゲンに対する過敏反応で湿疹や丘疹、痒みを伴った発疹が生じます。主に若齢犬に多く見られ、原因抗原の特定が難しいのが特徴です。アレルゲン除去が困難なため、治療期間も長期に及びます。食物アレルギーも似たアレルギー反応を引き起こし皮膚症状を示します。原因食材の特定が治療の鍵となります。
ノミ・ダニアレルギーや疥癬では、ノミ・ダニに対するアレルギー反応でかゆみと発疹などの皮膚症状が現れます。駆除が治療の基本ですが、再感染に注意が必要です。
細菌や真菌感染症も発疹の代表的な原因で、膿疱性皮膚病変や湿疹を伴うことがあります。抗生物質や抗真菌薬による治療が基本となります。
いずれもアレルギー反応や感染が関与しており、的確な診断と適切な治療が必要不可欠です。早期発見、早期治療が大切です。
2. 発見方法と対策
発疹には赤み、腫れ、丘疹、痒みなどの共通した特徴があります。部位別の傾向からある程度原因を推定できる場合もあります。例えば四肢にボツボツした発疹は疥癬が疑われますし、背中に脱毛と発疹はノミアレルギーを疑う材料となります。
治療では抗炎症薬と原因療法(アレルゲン除去、ノミ・ダニ駆除、抗生物質投与等)を行います。再発防止には清潔な環境とアレルゲンコントロールが非常に重要です。
予防には健康な皮膚状態の維持が大切です。栄養管理やストレスコントロール、過度な洗浄の回避などがポイントとなります。異変時の早期発見・早期治療も再発防止に有効な対策といえます。
3. 考えられる病気
- ノミアレルギー性皮膚炎
- アトピー性皮膚炎
- ツメダニ症
- 膿皮症
- 疥癬
- 脱毛症
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の体がかゆい症状の代表的な原因疾患として、アレルギー性皮膚疾患、寄生虫感染症、細菌・真菌感染症などが挙げられます。
アトピー性皮膚炎では、アレルゲンに対する過敏反応で全身的なかゆみが生じます。主に若齢犬に多く認められ、原因となるアレルゲンの特定が困難なのが特徴です。季節的な環境アレルゲンのほか、食物アレルゲンも関与すると考えられています。慢性的な炎症を伴い、二次感染のリスクも高いのが難点です。
ノミやダニなどの寄生虫感染もかゆみの主な原因の一つです。寄生部位を中心に強いかゆみが生じるのが特徴で、駆除薬による完全な除去が治療の要となります。再感染に注意が必要不可欠です。
細菌や真菌による各種皮膚感染症もかゆみを引き起こす代表例です。炎症を伴い、膿疱や湿疹、鱗屑などを伴うことも多く見られます。
いずれもかゆみが非常に強いため、治療はもちろんのこと、症状の緩和が重要視されます。
2. 発見方法と対策
かゆがり方や部位の広がりからある程度原因の推定が可能です。例えば全身的なかゆみはアトピー性皮膚炎が疑われますし、尾周囲のかゆみはノミアレルギーの可能性が高いと言えます。
治療では抗炎症薬や抗アレルギー薬によるかゆみ止めと、原因療法の併用が基本です。必要に応じて、アレルゲンの特定と除去。また、ノミ・ダニの駆除薬も高頻度で使われます。抗生物質や抗真菌薬の使用なども行います。
予防には清潔な環境と栄養バランスのとれた食事による皮膚の健康維持が非常に重要です。早期発見・早期治療に努めることも再発防止には効果的です。
3. 考えられる病気
- ノミアレルギー性皮膚炎
- アトピー性皮膚炎
- ツメダニ症
- 膿皮症
- 疥癬
- アカラス症(ニキビダニ症、毛包虫症)
- 脱毛症
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬のフケが多い症状の主な原因としては、ノミやダニなどの寄生、アレルギー性皮膚疾患、皮脂腺の異常などが考えられます。
ノミやダニが原因の場合、寄生部位を中心にフケが増えるのが特徴です。背中や尾周囲に多いことが多く、強いかゆみを伴うこともあります。駆除薬による完全除去が治療の要となります。
アレルギー性皮膚疾患では全身的にフケが増加しがちです。代表的なアトピー性皮膚炎では、アレルゲン除去が治療の基本となります。
皮脂腺の異常では皮膚が脂漏性となり、全身的にフケの増加がみられます。原疾患の治療が必要不可欠となります。
いずれも皮膚症状を引き起こすため、フケの増加に気づいたら早期に原因を特定し、適切な治療を開始する必要があります。
2. 発見方法と対策
フケの増加部位からある程度原因が推定できます。ノミ・ダニによるものでは寄生部位に。アレルギー性皮膚疾患では全身にわたるフケの増加がみられる傾向があります。
治療では原因疾患の治療が基本です。ノミ・ダニ駆除、アレルゲン対策、皮膚症状の改善などが必要になります。定期的なフケのチェックと早期発見に努めることも再発防止には重要です。
予防には清潔な環境と栄養バランスのとれた食事による皮膚の健康管理が非常に大切です。適切なケアで皮膚の異常を防ぎましょう。
3. 考えられる病気
- ノミアレルギー性皮膚炎
- ツメダニ症
- 疥癬
- 脱毛症
- 続発性脂漏症
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の体臭が気になる症状の主な原因は、皮膚疾患によるものが多いです。代表的なのが脂漏症です。
脂漏症は皮脂腺の異常分泌により発症し、皮膚が脂漏性となることで強い体臭を伴います。背中から尾の周囲に多く見られるのが特徴です。アレルギーやホルモン異常が誘因となることがあるほか、他の皮膚疾患に続発することもあります。
その他、皮膚の細菌感染症である皮膚糸状菌症(白癬)などでも体臭の増加がみられます。これらの感染症に対しては、抗生物質や抗真菌剤等の内服薬・外用薬・シャンプーの使用が治療の基本となります。
いずれも皮膚疾患が関与しているため、早期発見と原因療法が必要不可欠です。
2. 発見方法と対策
体臭の増加には皮膚の異常が伴うことが多いため、皮膚の状態を確認するのが第一歩です。脂漏性皮膚変化や発疹、脱毛などに注意が必要です。
治療では原因疾患の改善が基本となります。脂漏症に対しては皮膚の洗浄と保湿が重要です。定期的な皮膚チェックも再発防止には効果的です。
予防には清潔な皮膚の維持がカギとなります。適切な食事と運動で皮膚の健康を保つことが大切です。
3. 考えられる病気
- 続発性脂漏症
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
膿皮症は、ブドウ球菌などの細菌が皮膚に感染することで起こる化膿性の皮膚疾患です。細菌感染の深さや程度によって、浅在性、表在性、皺壁性、深在性などに分類されます。主な症状は、発赤、脱毛、発疹(ブツブツ)、膿疱、かさぶたなどです。顔や腋窩、股関節、指の間などに好発します。
膿皮症の原因は、ブドウ球菌をはじめとする細菌が皮膚に感染することによります。不衛生な環境、皮膚の擦り傷や噛み傷が細菌感染の端緒となることが多いのです。他にも、皮膚の老化や栄養不良、アレルギー性皮膚炎やニキビダニ症などの基礎疾患、皮膚に合わないシャンプー成分や過度の洗浄が関与すると考えられています。老齢の犬は皮膚機能が低下しがちなため、膿皮症にかかりやすくなります。また、遺伝的な素因も関係していると言われていて、ジャーマンシェパード種などは膿皮症になりやすい傾向があります。汚れた環境下で飼育されている犬ほど膿皮症にかかるリスクが高く、清潔な飼育環境を心がけることが予防の基本となります。
2. 発見方法と対策
膿皮症の発見には、皮膚の観察が重要です。顔や腋窩、股関節、指の間などを確認し、発赤、脱毛、発疹、膿疱、かさぶたなどの異常がないか注意深く観察しましょう。発熱や腫れ、痛みを伴う場合は、深在性膿皮症の可能性があります。
治療では、原因となった細菌に対する抗生物質投与と薬用シャンプーによる洗浄が基本です。基礎疾患がある場合はその治療も必要です。軽症の場合は抗生物質の経口投与で治癒しますが、重症の場合は入院しての治療が必要になることもあります。また、膿皮症は再発しやすい疾患なので、治療終了後も定期的な観察が大切です。予防には清潔な飼育環境の確保、栄養管理、適切なシャンプー使用が重要となります。日頃から皮膚の健康状態に気を配ることが大切です。
3. 考えられる病気
- アレルギー性皮膚炎
- 膿皮症
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬のしこりやはれができる症状の代表的な原因としては、良性腫瘍の脂肪腫や、悪性腫瘍の悪性リンパ腫、乳腺腫瘍、肥満細胞腫などがあります。
脂肪腫は老齢犬に多く見られる良性の脂肪腫瘍で、全身の皮下組織に好発するのが特徴です。腫瘍はゆっくりと成長するため、気づかれにくいのが難点です。対照的に、悪性リンパ腫や肥満細胞腫などの悪性腫瘍は、放置すると転移を起こし重症化する可能性が高く、早期発見が極めて重要です。
乳腺腫瘍も代表的な疾患で、避妊手術の有無が発生リスクと深く関係していることが知られています。性ホルモンの影響が強く示唆されています。
いずれも早期発見と適切な診断が大切です。放置すれば進行の恐れがあるため、早めの対応が必要不可欠です。定期検診が重要な役割を果たします。
2. 発見方法と対策
しこりの発見には体の触診が基本となります。大きさや硬さ、発生部位からある程度の推定は可能です。例えば、乳腺にできた柔らかいしこりでは乳腺腫瘍が疑われます。
治療は腫瘍の性質に応じて異なり、悪性腫瘍では抗がん剤投与や放射線治療が必要になる場合が少なくありません。早期発見と早期治療が予後に大きな影響を与えます。
予防には定期検診の実施と早期発見が極めて重要です。異常を感じたらできるだけ早く専門医の診断を受けることが大切です。早期発見に努めることが予防と治療のカギを握っています。
3. 考えられる病気
- 脂肪腫
- 乳腺腫瘍
- 肥満細胞腫
- 悪性リンパ腫
- クリプトコッカス症
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の肛門のまわりにしこりができる代表的な原因は、肛門周囲腺腫です。これは肛門周囲の腺組織に良性の腫瘍が形成される疾患です。
主に去勢されていないオス犬の老齢期に多くみられ、男性ホルモンの影響が示唆されています。腫瘍が肛門周囲の腺組織に限局しているのが特徴で、放置すると排便困難などを引き起こします。
早期発見と適切な治療が必要不可欠な疾患といえます。去勢手術が予防法となります。
2. 発見方法と対策
肛門周囲の触診により硬いしこりの有無を確認するのが発見方法の基本です。大きさや部位から肛門周囲腺腫と診断できます。
治療は外科的切除が主体となりますが、再発の可能性が高いため注意が必要です。同時に去勢手術を行うことが一般的です。
予防には若齢時の去勢が最も有効です。定期的な肛門周囲の確認も第二の予防法として重要といえます。
3. 考えられる病気
- 肛門周囲腺腫
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の皮膚がうすくなる症状の主な原因は、ホルモン異常による内分泌疾患です。代表的なのがクッシング症候群です。
クッシング症候群は副腎皮質ホルモンの過剰分泌により起こり、皮膚のうすさや脱毛などを引き起こします。6歳以上の中高年犬に多く見られ、飲水量や体重の変化など、様々な併発症を伴うのが特徴です。クッシング症候群の場合、放置すれば命に関わる重篤化の可能性が高いため、早期発見が極めて重要です。
ほかに甲状腺機能低下症なども皮膚のうすさを招くことがあります。いずれもホルモン異常が原因であるため、適切なホルモン補充治療が必要不可欠です。
2. 発見方法と対策
皮膚のうすさには他の症状も伴うことが多いため、飲水量や体重の変化、脱毛なども合わせて確認します。部位的な偏りもチェックポイントです。
治療は原因となるホルモン異常の改善を図ることが基本です。クッシング症候群では副腎皮質ホルモンの調整、甲状腺機能低下症では甲状腺ホルモン補充などが行われます。
定期検査で異常を早期発見することや、ホルモン剤を適正に使用することが予防に大切です。皮膚の健康管理も再発防止には重要なファクターといえます。
3. 考えられる病気
- 脱毛症
- クッシング症候群
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の皮膚が黒くなる症状の主な原因は、甲状腺機能低下症などの内分泌疾患です。
甲状腺機能低下症は甲状腺ホルモンの分泌低下により発症し、皮膚が黒ずむことを特徴とします。脱毛や体重増加などの症状も伴い、腫瘍など他の疾患と区別がつきにくいのが難点です。中高年の中大型犬に多く見られるため、高齢のうちに定期検査が必要です。
クッシング症候群でも皮膚が黒ずむことがあり、副腎皮質ホルモンの過剰分泌が原因のホルモン異常といえます。肥満などの症状も伴います。
いずれも放置すれば重症化のおそれがあるため、早期発見が極めて重要となります。
2. 発見方法と対策
皮膚の黒ずみには脱毛や体重変化などの他の症状も伴うことが多いため、総合的に判断します。甲状腺機能低下症の可能性が高い場合もあります。
治療は原因となるホルモン異常の改善が基本です。甲状腺機能低下症では甲状腺ホルモンの補充、クッシング症候群では副腎皮質ホルモンの調整などを行います。
予防には定期検査による早期発見と、適正なホルモン投与が極めて重要です。異常の兆候を見逃さないことが大切です。
3. 考えられる病気
- 脱毛症
- 甲状腺機能低下症
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の皮膚や粘膜の一部が青紫色になる症状の代表的な原因は、酸素欠乏によるものです。
心疾患や呼吸器疾患などで酸素の取り込みや循環が障害されると、チアノーゼが生じます。心房中隔欠損症では心臓の中隔に穴が空いて酸素飽和度が低下し、肺水腫では肺に水分がたまって肺胞が閉塞され酸素吸収が阻害されます。気管支虚脱でも気管の変形により酸素取り込みが低下します。
重度の熱中症で体温調節能力を超えると、細胞レベルでの酸素欠乏が生じてチアノーゼがみられます。
いずれも酸素不足が長引けば重篤化の恐れが高いため、早期発見が必要不可欠です。チアノーゼが確認された際には迅速な対応が求められます。
2. 発見方法と対策
チアノーゼの兆候は口腔粘膜や眼球粘膜の青紫さ(青白さ)です。呼吸困難など他の症状の有無も確認します。部位的なチアノーゼか全身性かも判断材料となります。
治療では原疾患の改善とともに、酸素投与が行われることが多いです。時には人工呼吸器が必要になることも。酸素欠乏から脳障害が生じる恐れもあるため、酸素投与は欠かせません。
予防には呼吸器疾患や心疾患の早期発見・早期治療が重要です。運動の管理もチアノーゼ予防のためには有効です。早期発見のための定期検査が予防策として重要といえます。
3. 考えられる病気
- 熱中症
- 気管虚脱
- 肺水腫
- 心房中隔欠損症
皮膚の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
被毛の症状
1. 原因と傾向
犬の毛が抜ける主な原因には、アレルギー性皮膚疾患、外部寄生虫感染、内分泌疾患、腫瘍などがあります。
アトピー性皮膚炎では全身的な掻痒感と脱毛が特徴的です。原因となるアレルゲンを特定し、接触を避けることが治療の基本です。特定のアレルゲンとの関係が明らかになれば、それを除去することで症状の改善が期待できます。
ノミやダニ、ツメダニなどの寄生虫感染では局所的な脱毛が起こります。寄生部位の掻痒感が強く、二次的な細菌感染の可能性もあります。駆虫薬の定期的な使用と、環境衛生管理が重要です。
甲状腺機能低下症、クッシング症候群などの内分泌疾患では対称性の脱毛が見られるのが特徴です。皮膚が薄くなったり、脂漏性になることもあります。正しい診断と継続的な内分泌治療が必要不可欠です。
がんによる脱毛では、腫瘍部位の局所的な脱毛が特徴的です。扁平上皮癌、肥満細胞腫などでみられます。早期発見と迅速な対応が大切です。
ストレスなども抜け毛の原因となります。脱毛の部位や対称性、掻痒感の有無などから原因を推定します。
2. 発見方法と対策
脱毛の程度や部位などの特徴から原因を推測し、他の皮膚症状の有無も確認します。治療は原因疾患の治療が基本です。
アレルギー性なら除去と抗アレルギー薬の使用、寄生虫感染なら駆虫薬、腫瘍なら外科的切除や内分泌疾患ならホルモン補充療法など、原因に応じて行います。対症療法として、脱毛部位へのステロイド外用薬の使用もあります。
予防には愛犬の健康な生活環境づくりが重要です。適度な運動、ワクチン接種、栄養管理、寄生虫対策を行うことで、疾病の発生を未然に防ぎます。ストレスは脱毛の大きな原因の一つなので、飼い主の穏やかな接し方が重要です。また、早期発見には皮膚の定期的なチェックが有効です。少しでも異常があれば速やかに獣医師の診断を受けることをおすすめします。
3. 考えられる病気
- 脱毛症
- ノミアレルギー性皮膚炎
- ツメダニ症
- 続発性脂漏症
- 膿皮症
- 疥癬
- アカラス症(ニキビダニ症、毛包虫症)
- 皮膚糸状菌症(白癬、皮膚真菌症)
- クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
- 甲状腺機能低下症
- 肥満細胞腫
- 扁平上皮がん
被毛の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の毛ヅヤが悪くなる主な原因は、栄養不足、皮膚疾患、寄生虫感染などです。
栄養不足ではタンパク質や脂肪酸、ビタミン、ミネラルの欠乏が毛ヅヤの低下につながります。特に脂肪酸不足は毛ヅヤに大きな影響を及ぼします。
皮膚疾患の場合、炎症やかゆみによる毛づやの損傷が起こります。代表的なのはアトピー性皮膚炎です。
寄生虫感染では寄生のために毛包が障害されることがあります。ノミやダニ、ツメダニなどの外部寄生虫が好発部位の毛ヅヤを損なうケースが多くみられます。
いずれも毛ヅヤが失われ、毛先が切れやすくなり、毛全体がだらしなく見えるようになります。ストレスも毛ヅヤに影響し、過度のストレスがかかると、自律神経の変化を通じて皮脂分泌が低下し、毛ヅヤの低下につながると考えられています。
2. 発見方法と対策
毛ヅヤの低下は、毛を平らに撫でて光沢がないか確認します。薄毛や脱毛、皮膚疾患の兆候がないか注意しつつ、食事内容や寄生虫感染の有無も調べます。
対策として栄養改善、皮膚病の治療、寄生虫駆除など原因に応じた薬物治療を行います。
ストレスが原因なら、飼育環境の改善や散歩などの運動機会を増やすことで改善できる場合があります。ブラッシング等で皮脂を補うケアも効果的です。
治療に反応しない場合は、甲状腺機能低下症など内分泌疾患の可能性も考えられますので、動物病院で確認する必要があります。
食事内容の見直しだけでなく、愛犬の生活環境やストレス要因を総合的に判断し、毛ヅヤ低下の原因を探っていくことが大切です。
3. 考えられる病気
- 脱毛症
- ツメダニ症
- 甲状腺機能低下症
被毛の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
呼吸器の症状
1. 原因と傾向
犬の咳の原因には、気管支炎、肺炎、心疾患、寄生虫感染などがあります。
気管支炎では季節変動に伴う発作性の咳が特徴的です。症状の悪化は気温の変化に関係し、管理された環境下では重症化しにくい傾向があります。ウイルスや細菌、真菌などの感染が誘因となることが多く、二次感染の防止が重要です。
肺炎では発熱や食欲不振を伴います。原因となる細菌・ウイルス感染の有無を確認する必要があります。特に痰の細菌培養検査が有効的です。
心疾患の場合、運動時に呼吸困難を示すことがあります。心不全による肺うっ血が咳の誘因となっている可能性が考えられます。心エコー検査等で心機能を評価します。
フィラリア症では慢性的な咳がみられ、四肢の浮腫も特徴的です。糸状虫予防薬の投与歴を確認することが診断の手がかりとなります。咳の性状や他の症状の有無から原因を推測する必要があります。
2. 発見方法と対策
咳の触発因子、時間帯、性状などの特徴を把握します。
併発症状の有無も確認し、原因疾患の特定に努めます。気管支炎なら湿潤環境の改善、心疾患なら強心薬の投与、寄生虫感染なら駆虫薬の使用など、原因に応じた治療が基本となります。呼吸管理や鎮咳薬による対症療法も併用します。
予防にはワクチン接種、環境管理、寄生虫対策が重要です。定期的な健康診断で異常を早期発見し、適切な治療介入を心がけることが大切です。
また、風邪をひきやすい季節の対策として、適度な保温や湿度管理、運動量の調整も有効的です。ストレスは咳の誘因になりやすいので、飼育環境の改善にも注力しましょう。
3. 考えられる病気
- フィラリア症(犬糸状虫症)
- 肺炎
- 肺水腫
- 犬ジステンパーウイルス感染症
- ケンネルコフ(伝染性気管支炎)
- 気管虚脱
- 僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁逆流症)
- 心室中隔欠損症
- 拡張型心筋症
- 悪性リンパ腫(リンパ肉腫)
呼吸器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の呼吸がゼーゼーと荒くなる主な原因は、気管支炎、気管虚脱、心不全などです。
気管支炎では炎症により気道が狭窄し呼吸路の抵抗が増大するため、呼吸困難になります。
ウイルスや細菌、アレルゲンなど様々な原因が考えられ、季節変動もある点が特徴です。冬季に発症しやすく、症状の変動性が大きいのが特徴です。
気管虚脱では気管の変形により気流が阻害され呼吸が困難に。小型犬に多く、興奮時に顕著になります。気管軟骨の変性が原因で、遺伝的素因が示唆されています。
心不全での肺水腫では肺胞内に浸出液が貯留し、肺への酸素交換が低下することで呼吸数が増加します。心疾患の有無を確認する必要があります。
発作的な呼吸困難は喘息の可能性もあります。アレルギーが関与していることが多く、発作的な変動が特徴です。呼吸のリズムや音から原因をある程度推定可能です。
2. 発見方法と対策
呼吸時の喘鳴音の有無、チアノーゼや四肢浮腫などの確認とともに、胸部レントゲン検査や心電図検査で原因疾患の確定を図ります。気管支拡張薬や利尿薬、酸素投与による呼吸管理、ステロイド薬による炎症抑制、原因となる疾患の治療を行います。呼吸状態の定期的なモニタリングと早期発見が大切です。
飼育環境の改善やストレス緩和も呼吸困難の軽減に有効です。
呼吸器疾患に対する定期検診の実施も重要な予防法といえます。
感染症や寄生虫対策、ワクチン接種のほか、運動や栄養管理にも注意が必要不可欠です。
3. 考えられる病気
- フィラリア症(犬糸状虫症)
- クリプトコッカス症
- トキソプラズマ症
- 鼻炎
- 副鼻腔炎
- 肺炎
- 肺水腫
- 肺動脈狭窄症
- 気管虚脱
- 胃拡張・胃捻転症候群
- 拡張型心筋症
- 心室中隔欠損症
- 僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁逆流症)
- 悪性リンパ腫(リンパ肉腫)
- 免疫介在性溶血性貧血(IMHA)
- 熱中症(熱射病、日射病)
呼吸器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬が血を吐く主な原因は、外傷、寄生虫感染、消化管疾患、凝固障害などです。
外傷では鼻出血や口内損傷による血の混入が考えられます。交通事故などの強い衝撃による内臓損傷も念頭に置く必要があります。
フィラリア症では感染初期や少数寄生の場合、ほとんど症状はみられません。しかし、寄生されてから年月が経過すると、咳や息が荒くなるなどの呼吸器症状が徐々にひどくなり、四肢のむくみ、腹水(お腹に水がたまって膨れること)などが見られ、散歩中に休む回数が増えるなど運動を嫌がるようになります。さらに進行すると、喀血(かっけつ:血を吐くこと)や失神を起こすことがあります。
消化管疾患では胃炎や潰瘍、腫瘍が出血の原因となりえます。特に老齢犬で複数の原因が重なることも。血小板減少症などの凝固障害では自然出血の可能性もあります。
2. 発見方法と対策
他の症状の有無の確認とともに、出血の量や色調、嘔吐の有無などから原因をある程度推測可能です。
フィラリア症の治療方法には、内科的療法と外科的療法があります。
内科的療法は、薬剤によって体内のフィラリアを駆除する療法です。ただし、多数感染の場合に一度に大量の虫を駆除すると、虫体が肺動脈に詰まって命にかかわるおそれがあるので、慎重に投与する必要があります。外科的療法は、心臓や大動脈に寄生したフィラリアを外科的手術で取り出す療法で、急性期のフィラリア症に用います。検査結果や体調、年齢などを考慮して、これらの治療が実施できないと判断する場合は、症状に応じて処方食や薬剤などを用いて、腹水を減らす、咳を抑えるといった対症療法をおこないます。
胃潰瘍では制酸剤等の投与も有効です。凝固障害では血液検査の実施が重要です。出血量が多ければ輸血も考慮します。
原因に応じた治療と予防が大切です。定期検診による早期発見にも努めるべきです。
3. 考えられる病気
- フィラリア症(犬糸状虫症)
- 胃潰瘍
- 外傷
呼吸器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
消化器の症状
1. 原因と傾向
犬が吐いてしまう原因には大きく分けて2つあると考えられています。
1つは消化器系の問題によるもの、もう1つはその他の病気や体調の変化に関連したものです。
消化器系の問題では、食べ物に関連した原因が最も多く見られます。
例えば、食べ過ぎてしまった時、急に食べ物を変更した時、腐った食べ物を食べてしまった時などに嘔吐が起こりやすいです。
食べ物アレルギーや食品不耐症も原因の1つです。アレルギーを起こしやすい食材を与え続けていると嘔吐を繰り返すこともあります。
また、胃腸の異常や炎症、腸内寄生虫などによっても嘔吐が引き起こされます。胃炎や腸炎、寄生虫の大量寄生などで、胃腸の粘膜が刺激されることで嘔吐反射が起こります。
一方で、肝臓疾患、腎臓疾患、膵臓疾患などの全身疾患が原因となることもあります。これらの疾患では、体内の老廃物の排泄障害や、体内環境の変化により嘔吐が起こります。
肝不全や腎不全、高カルシウム血症などで嘔吐が見られるケースが報告されています。
また、妊娠中のメス犬では、つわりに似た症状で嘔吐が起こることもあります。
傾向として、子犬や老犬は吐きやすいといわれています。
子犬は新しい環境や食べ物の変化に敏感で、ストレスなどで嘔吐しやすいです。
一方、老犬は消化器官の機能低下があるため吐きやすいと考えられています。胃酸分泌能力が低下し、食べ物をうまく消化できないことがあります。
体質的に吐きやすい犬種も存在すると言われており、飼い主の方はご自分の犬の傾向を把握することが大切です。
2. 発見方法と対策
まず、嘔吐の回数や頻度、その量や内容を確認し、記録しておきましょう。吐いた後の犬の様子も観察することが大切です。この情報は獣医師の診断の手掛かりとなります。
次に、吐いたものをできるだけ保存しておくことをおすすめします。吐いた物の色やにおい、量、固形か液体かなどを具体的写真やメモに書き留めておけば、獣医師が内容物を検査することで原因の特定に役立ちます。
吐いたものを片付ける場合は、手袋とマスクを使用するなど、衛生面には十分気をつけてください。
対策としては、まず冷静に観察し、必要に応じて水分補給を行うことが重要です。吐いた後は脱水気味になっているので、少量ずつ水分を与えましょう。吐血や激しい嘔吐が見られる場合には、できるだけ早く獣医師に診てもらいましょう。
嘔吐が1日に数回見られたり、他の症状も伴ったりするケースでは、早めの受診が望まれます。
3. 考えられる病気
- 回虫症
- 犬コロナウイルス感染症(コロナウイルス性腸炎)
- 犬ジステンパーウイルス感染症
- 犬パルボウイルス感染症
- レプトスピラ症
- 下痢
- 腸閉塞
- 緑内障
- 犬伝染性肝炎
- 膵炎(すい炎、膵臓炎、すい臓炎)
- 腎不全
- 犬の糸球体腎炎
- 尿毒症
- アジソン病(副腎皮質機能低下症)
- そけいヘルニア(鼠径ヘルニア)
- 子宮蓄膿症
- 犬の免疫介在性溶血性貧血(IMHA)
- 犬の肝臓がん(肝臓腫瘍)
- 肥満細胞腫
- 悪性リンパ腫(リンパ肉腫)
- 熱中症(熱射病、日射病)
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の食欲不振の原因には大きく分けて2つあると考えられます。1つは病気に関連したもの、もう1つはストレスや環境の変化に関連したものです。
病気に関連した食欲不振では、慢性的な消化器疾患や腎臓病、肝臓病、糖尿病などの全身疾患が主な原因となります。これらの疾患では、体内環境の変化や症状の悪化に伴い、食欲が低下します。例えば慢性腎臓病では尿毒症により食欲が減退し、慢性肝疾患ではアンモニアの蓄積により食欲が低下することが知られています。また、感染症の場合も、発熱や炎症により食欲が損なわれることがあります。ウイルスや細菌による消化器感染では、嘔吐や下痢などの症状に伴って食欲不振が生じます。
一方、ストレス性の食欲不振は、引っ越しなどの環境の変化によって生じます。不慣れな環境下ではストレスが高まり、食欲がなくなると考えられています。この場合、体調などに特段の異常は認められません。ただし、ストレスが強い場合には、ストレス性胃炎などを併発することもあるので注意が必要です。ストレス性胃炎では、ストレスによる過度の胃酸分泌が原因で、食欲不振と嘔吐が特徴的です。
傾向としては、病気による食欲不振は高齢の犬に多く、ストレス性の食欲不振は生後1年未満の幼犬に多いと言われています。気難しい犬種も、ストレスに対する反応が大きく、食欲不振を起こしやすい傾向にあると考えられています。
2. 発見方法と対策
食欲不振に気づいた場合、まず食事の量を記録しておきましょう。1日の食事量がどの程度減少したのか、具体的な数値が診断の手掛かりとなります。また、吐き気や嘔吐がみられないかも確認します。
次に、体重の減少がないか毎日確認します。食事量の減少に伴い、徐々に体重も減っていくことが多いためです。体重の推移を記録しておけば、食欲不振の程度がわかります。体重が急激に減少した場合は重症と判断されます。
対策としては、まずエサを工夫して食欲を促すことが大切です。カロリーの高い食事に変更したり、水分を多めに与えたりすると良いでしょう。食欲増進剤の投与も検討できます。あわせて、定期的な獣医師の診察が必要です。食欲不振が1週間以上続く場合は、早めの受診が望まれます。
3. 考えられる病気
- 瓜実条虫症(犬条虫症)
- 鉤虫症
- 鞭虫症
- コクシジウム症
- バベシア症
- ライム病
- レプトスピラ症
- 犬ジステンパーウイルス感染症
- 犬コロナウイルス感染症(コロナウイルス性腸炎)
- 狂犬病
- 歯周病
- 虫歯
- 口内炎
- 緑内障
- 関節リウマチ
- 乳腺炎
- 肺炎
- 腸閉塞
- そけいヘルニア(鼠径ヘルニア)
- 心室中隔欠損症
- 門脈シャント
- 膵炎(すい炎、膵臓炎、すい臓炎)
- アジソン病(副腎皮質機能低下症)
- 腎不全
- 糸球体腎炎
- 尿毒症
- ネフローゼ症候群
- 膀胱炎
- 子宮蓄膿症
- 犬の免疫介在性溶血性貧血(IMHA)
- 犬の肝臓がん(肝臓腫瘍)
- 悪性リンパ腫(リンパ肉腫)
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の体重減少の原因には、主に2つのパターンがあります。1つ目は、病気に関連した食欲不振や吸収不良などによるものです。2つ目は、過度の運動や食事量の不足によるものです。
病気に関連した体重減少では、慢性的な消化器疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、糖尿病などが代表的です。これらの疾患では、食欲低下や栄養吸収障害などにより体重が減少します。また、悪性腫瘍などの疾患では、代謝亢進による消耗性の体重減少がみられます。
一方、過度の運動や食事量の不足による体重減少は、病気とは無関係に生じます。運動量の増加に合わせて食事量が不足すると徐々に体重が減っていきます。ストレスなどで食欲が低下し、食事量が減ることも体重減少の原因となります。
傾向としては、病気に関連した体重減少は高齢犬に多く、運動や食事不足による体重減少は若齢犬に多いとされています。
2. 発見方法と対策
体重が減少しだした場合、まずは体重の推移を記録しましょう。体重がどの程度のペースで減っているかが重要な情報となります。食事量の変化も記録しておきましょう。
次に、体重減少に伴う食欲低下や元気の低下がないか確認します。これらの症状がある場合、病気の可能性があります。
対策としては、まずカロリーを増やした食事に変更することが有効です。また、こまめな水分補給も重要です。原因が特定できない場合は推定困難なため、早めの受診が望まれます。
3. 考えられる病気
- コクシジウム症
- ジアルジア症
- 回虫症
- 鞭虫症
- 糞線虫症
- 下痢
- 糖尿病
- 心室中隔欠損症
- 門脈シャント
- 肝臓がん(肝臓腫瘍)
- アジソン病(副腎皮質機能低下症)
- クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
- 糸球体腎炎
- 腎不全
- 尿毒症
- 尿崩症
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の体重増加の主な原因は、過食と運動不足による肥満です。
肥満はエネルギー摂取量が消費量を上回ることで起こります。過度にエサを与え過ぎたり、エサのカロリーが高すぎたりすることで体重が増えていきます。運動不足も肥満の大きな原因となります。運動によるカロリー消費が十分でないと、摂取カロリーがそのまま体脂肪として蓄積されてしまいます。
肥満しやすい犬種も存在し、ラブラドール・レトリバー、ビーグル、コーギー等が代表例です。これらの犬種は食い意地が強く、食事管理が甘いと容易に肥満が進行します。気質的に運動を嫌う犬種も肥満しやすい傾向にあります。生来、体を動かしたがらない性質の犬ほど運動不足に陥りやすいためです。
一方で、病気による体重増加もあります。クッシング症候群、低甲状腺機能症、インスリン関連等の内分泌疾患では、ホルモン異常が食欲増進、代謝低下をもたらし、体重増加を来します。これらの疾患は加齢とともに発生頻度が高くなるため、高齢犬の体重増加の原因として疑う必要があります。
2. 発見方法と対策
体重が増えてきた場合、まずは1日のエサの量と内容を確認しましょう。過食が原因となっていないかを確認する上で重要な情報です。運動量の変化も確認します。1日の散歩時間や活発度が以前より低下していないかをチェックしましょう。
次に、体重増加のペースを記録していきます。体重が月に何キロずつ増えているかを把握することが大切です。急速に増えている場合は病気の可能性も考えられます。他の症状の有無も重要な観察ポイントです。
対策としては、適正な食事量と内容の調整、運動量の増加が基本となります。病気の可能性がある場合は動物病院での検査が必要不可欠です。採血や画像検査により、病気の有無を確認することができます。
3. 考えられる病気
- 甲状腺機能低下症
- クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の便秘の主な原因は、食事内容の変更や運動不足による便の水分量の低下、病気による腸の動きの低下などが考えられます。
食事内容を急に変更した場合、腸内環境が変化し、便秘を招くことがあります。例えば、高炭水化物のドライフードから低炭水化物のウェットフードへの変更時には注意が必要です。運動不足で腸の蠕動運動が低下すると、便の輸送が滞り便秘になりやすくなります。運動量の減少は便秘の大きなリスクファクターの一つです。
一方、病気による便秘では、腸炎等の消化器疾患、神経疾患、腫瘍等が原因となります。これらは腸の動きを鈍くさせたり、腸管を圧迫することで便秘を引き起こします。例えば、大腸炎では腸壁の炎症により蠕動運動が低下します。また、神経疾患では腸を支配する自律神経の異常が関与します。
傾向としては、食事変更や運動不足による便秘は比較的若齢の犬に、病気に伴う便秘は中高齢の犬に多く見られるとされています。若齢犬ほど食事変更などの影響を受けやすいためと考えられます。
2. 発見方法と対策
便秘に気づいたら、排便間隔と便の量、硬さを記録しましょう。排便間隔が長く、少量の硬い便を排出するようなら便秘と考えられます。具体的には48時間以上排便がなければ便秘と判断されます。
排便時の苦痛様反応も重要なポイントです。疼痛を伴う便秘は病気による可能性が高いので要注意です。激しい痛みを訴える様子は緊急を要するサインとなります。
対策としては、食事内容の調整、水分補給、運動の増加が基本となります。病気による便秘の可能性がある場合は、獣医師の診断が必要不可欠です。
3. 考えられる病気
- 腸閉塞
- 前立腺肥大
- 前立腺腫瘍
- さいヘルニア(臍ヘルニア)
- そけいヘルニア(鼠径ヘルニア)
- えいんヘルニア(会陰ヘルニア)
- 肛門周囲腺腫
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の下痢には様々な原因があり、症状も原因によって異なります。主な原因としては、食事に関するもの、感染症、寄生虫感染、腸内疾患、ストレス等があります。
食事に関する下痢では、食べ物の変更、過食、食物アレルギーなどが原因となります。例えば、長期間同じフードを食べていた犬が新しいフードに変更した場合、腸内環境の変化に犬の腸がすぐには順応できずに下痢を起こすことがあります。また、高脂肪食や人食を過食した場合にも下痢が生じます。食物アレルギーがある犬に、アレルゲンとなる食材を与えると下痢が起こります。乳糖不耐症の犬に牛乳を与えても下痢の原因となります。
感染症による下痢では、ウイルスや細菌感染が関与し、パルボウイルス、ジステンパーウイルス、大腸菌などが代表的です。これらの感染では、ウイルスや細菌が腸管細胞を障害し、水分吸収能が低下して水様性の下痢を起こします。パルボウイルスやジステンパーウイルスでは、重度の下痢、脱水、ショックを伴うこともあります。大腸菌感染では、赤痢菌やリステリア菌などの病原性大腸菌が原因となります。
寄生虫感染では、回虫、鞭虫、原虫などの寄生が下痢の原因となります。回虫や鞭虫の寄生は腸管障害をもたらし、寄生虫自体やその排泄物が下痢の原因となります。原虫の一種であるジアルジアは、小腸での栄養吸収不全を引き起こし下痢をもたらします。
腸内疾患に起因する下痢もあり、腸炎、膵炎、腫瘍などが下痢の原因となることがあります。腸炎は腸の炎症反応を引き起こし、膵炎では膵酵素の活性化により下痢が生じます。悪性腫瘍は腸管の狭窄や潰瘍を形成し下痢を引き起こすことがあります。
ストレスによる下痢もよく見られ、環境の変化や不安などが引き金となって交感神経の緊張が高まることで起こります。新しい環境への不安、飼い主との長期別離等がストレスとなり下痢の原因となります。
症状としては、水様性の下痢、便回数の増加、血便や粘液便の排泄が見られます。回虫や鞭虫感染では黒色便を呈することもあります。感染症による下痢では、発熱や全身状態の悪化を伴うこともあります。慢性の下痢では体重の減少も伴います。下痢の性状や他の症状から、原因の特定につながることがあります。
2. 発見方法と対策
犬の下痢の治療では、まず正確な原因を特定することが重要です。原因に応じて、抗菌剤、駆虫薬、食事療法などの治療を行います。
感染症による下痢では、原因となるウイルスや細菌に対して、有効な抗菌剤を投与します。複数の病原体の関与が疑われる場合は、広域スペクトルの抗菌剤が選択されることもあります。
寄生虫感染による下痢に対しては、原因となる寄生虫に有効な駆虫薬が投与されます。鞭虫にはフェンベンダゾール等、回虫にはピランテルパモ酸塩等が用いられ、原虫感染症にはメトロニダゾール等が用いられます。
食事性の下痢では、原因食品の除去、低残渣食(ていざんさしょく)、消化の良い食べ物を少しずつ与える等の食事療法が基本となります。
脱水症状がある場合は、輸液治療も並行して行います。生理食塩水やブドウ糖液の輸液が行われ、水分や電解質の補給が図られます。
下痢の予防には、適切なワクチン接種、駆虫の実施、食事内容の管理、ストレスの回避などが挙げられます。混合ワクチン、コロナウイルスワクチン、パルボウイルスワクチンの接種が、下痢の原因となるウイルス感染の予防に有効の場合もあります。
駆虫薬による駆虫は、寄生虫感染による下痢の予防に役立ちます。とくに回虫、鞭虫の駆虫は重要です。
食事内容の変更は段階的に行うことが大切です。急激な変更は腸内細菌叢の変動を招き下痢のリスクが増大します。
適度な運動と健康管理を心がけることも、下痢の予防につながります。清潔な飼育環境の維持も重要なポイントです。
以上のように、犬の下痢の治療と予防には、原因の特定と対策が欠かせません。獣医師の指導を受けることも重要です。
3. 考えられる病気
- エキノコックス症(多包条虫症)
- コクシジウム症
- ジアルジア症
- トキソプラズマ症
- マンソン裂頭条虫症
- レプトスピラ症
- 犬コロナウイルス感染症(犬コロナウイルス性腸炎)
- 犬ジステンパーウイルス感染症
- 犬パルボウイルス感染症
- 瓜実条虫症(犬条虫症)
- 糞線虫症
- 鞭虫症
- 鉤虫症
- 回虫症
- 腸閉塞
- 尿毒症
- アジソン病(副腎皮質機能低下症)
- 肝臓がん(肝臓腫瘍)
- 犬伝染性肝炎
- 膵炎(すい炎、膵臓炎、すい臓炎)
- そけいヘルニア(鼠径ヘルニア)
- 子宮蓄膿症
- 悪性リンパ腫(リンパ肉腫)
- 肥満細胞腫
- 熱中症
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
血便は、大腸や小腸、肛門周囲の病変からの出血が原因となります。
大腸性の血便の原因としては、大腸炎、大腸腫瘍、寄生虫感染などがあります。大腸炎はストレスや食事の急激な変更、ウイルスや細菌、寄生虫による感染が引き金となり起こります。例えば、飼い主の転居や留守がちになることでストレスがたまり、大腸炎を発症することがあります。また、肉中心の食事を長期間続けていた犬を急に穀物食に変更した影響で、大腸炎が生じることもあります。大腸寄生虫の感染も大腸炎の原因となりえます。
大腸腫瘍では、特に高齢犬に直腸肛門腫瘍が比較的多く見られます。この腫瘍は便秘や血便を引き起こします。
一方、小腸性の血便は、食物アレルギー、寄生虫感染、小腸腫瘍などが主な原因です。食物アレルギーのある犬がアレルゲンとなる食材を摂取することで、小腸炎を発症し血便を伴うことがあります。また、鞭虫や回虫などの寄生虫感染が、小腸炎や肉芽腫を形成し、血便をもたらすことがあります。
さらに、肛門周囲の病変からの出血では、肛門腺炎、痔核、外傷が原因としてあげられます。肛門腺炎は肛門腺の炎症で、排泄時の血便を特徴とします。痔核は肛門周囲の静脈のうっ血や腫れで、便秘による過度な排泄努力が原因となることがあります。外傷については、肛門周囲へのかみ傷や異物の挿入などで生じることがあります。
このように、血便をきたす原因は多岐にわたりますが、便の性状や量、回数、排泄時の痛みの有無、飼い主の観察などから、ある程度原因の特定が可能です。
2. 発見方法と対策
血便がみられた場合、まず便の色や性状、量、回数、排泄時の様子などを詳細に観察しましょう。
新鮮な出血では鮮紅色の血便となりますが、胆汁や腸内容物と混ざると黒色のタール便となるので、色だけでなく便の中身も確認します。
量と回数から、大腸や小腸のどちらに原因があるかを推測できます。大腸の場合は少量で頻回、小腸の場合は回数は少ないですが量が多くなる傾向があります。
排泄時の痛がりも原因推定の手がかりになります。
併せて、嘔吐やむかつき、食欲不振などの有無も観察する必要があります。
次に、寄生虫感染が疑われる場合は糞便検査、腫瘍が疑われる場合は内視鏡検査や生検などを受けて原因を特定します。
原因が判明したら、大腸炎なら食事療法、寄生虫なら駆虫薬、腫瘍なら抗癌剤や手術療法など、適切な治療を開始することができます。
以上のように、血便の性状の変化や排泄時の様子、検査結果を総合的に判断して原因を特定し、個別の症例に応じた治療を行うことが大切です。
3. 考えられる病気
- 下痢
- 鞭虫症
- 犬コロナウイルス感染症(コロナウイルス性腸炎)
- 犬パルボウイルス感染症
- レプトスピラ症
消化器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
泌尿器の症状
1. 原因と傾向
犬の血尿の原因としては、泌尿器系の感染症、結石、外傷、腫瘍などが主に考えられます。
泌尿器系の感染症では、細菌による膀胱炎や腎盂腎炎が代表的です。これらの感染では、炎症により出血が生じ血尿の原因となります。グラム陰性菌、グラム陽性菌による感染が多く見られます。
メス犬は生理構造的に尿道が短く、細菌の上行感染を受けやすいため、オス犬よりも膀胱炎などの泌尿器感染症が起こりやすい傾向があります。
結石は、腎臓や膀胱、尿道にできることがあり、尿の流れを阻害して出血を引き起こし血尿となります。ストルバイト結石やシュウ酸カルシウム結石、尿酸アンモニウム結石などが代表的です。これらの結石は尿のpH変化などと関連しています。
外傷では、交通事故などによる膀胱や腎臓への直接的な損傷が原因となります。外力によって臓器が破裂し出血が生じるため、外傷後は血尿の有無に注意が必要です。
腫瘍の場合は、腎臓、膀胱、前立腺などに発生した悪性腫瘍による出血が考えられます。転移性腫瘍の可能性もあり、他臓器の腫瘍からの転移による出血も起こりえます。
このほか、血液疾患や寄生虫感染もまれながら血尿の原因となり得ます。
2. 発見方法と対策
血尿の発見には尿の観察が重要で、膀胱炎などでは尿の混濁や悪臭も特徴的です。排尿時の痛みの有無も確認する必要があります。
対策としては、原因となる病気の治療が基本です。
感染症では原因菌の感受性を確認し、有効な抗生剤の投与が行われます。
結石では除去手術や内科的溶解が選択されます。
腫瘍では切除術や抗癌剤治療などが行われます。
予防には適度な水分補給、運動、食事管理が大切です。食事は過度の塩分・たんぱく質を避け、野菜を積極的に取り入れることが推奨されます。定期検診で早期発見に努めることも重要です。
放置すれば重症化する可能性が高いため、獣医師の診断と治療が不可欠です。早期発見、早期治療を心がけましょう。
3. 考えられる病気
- 前立腺肥大
- 尿道結石
- 膀胱結石
- 膀胱炎
- バベシア症
泌尿器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
尿の色の変化には、さまざまな原因が考えられます。
まず多く見られるのが、膀胱炎や尿路感染症による血尿です。膀胱炎は尿の正常なピンク色や黄色から赤みを帯びた色に変化させます。尿路感染症では、膀胱や尿道、腎臓に炎症が起こり、血尿を引き起こします。
次に多いのが、飲水量の変化に伴う尿の濃縮です。通常の飲水量よりも水分摂取が少ないと、尿が濃くなり黄褐色から茶褐色になります。
また、腎疾患や肝疾患、薬剤の影響によっても尿の色が変わることがあります。腎不全では尿が薄いピンク色から茶色に、肝疾患では茶色がかった黄色になります。
このように、尿の色の変化の原因にはいくつかのパターンがあり、他の症状と合わせて総合的に判断する必要があります。
2. 発見方法と対策
尿の色の変化がみられた場合は、次のような発見方法と対策があります。
まず飲水量の増減がないかを確認しましょう。飲水量が激減している場合は、水分補給をすれば自然に元の色に戻ることがあります。
他の症状の有無もチェックします。頻尿、排尿痛、血尿などの症状がある場合は、感染症の可能性が考えられます。
検尿や血液検査を行って、感染の有無や腎機能、肝機能を調べる必要があります。
原因が特定できれば、抗生剤の投与・腎機能改善の治療等といった対策を取ることができます。
以上のように、尿の色の変化と症状を確認し、必要に応じて検査を行って原因を特定することが大切です。変化が見られたら早めに受診しましょう。
3. 考えられる病気
- 膀胱結石
- 膀胱炎
泌尿器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬のおしっこの量が増える主な原因は、泌尿器系の疾患、代謝異常、ホルモン異常、心疾患などが考えられます。
泌尿器系の疾患では、膀胱炎、腎不全、尿路結石、尿道狭窄などが頻尿の原因となります。
膀胱炎では炎症により膀胱容量が低下し頻尿を引き起こします。
腎不全では糸球体濾過率の低下により尿量が増加します。
尿路結石は尿流出阻害で頻尿を来たします。
これらは膀胱内圧上昇や収縮力低下をもたらし頻尿の原因となります。
代謝異常では、糖尿病が代表的で、インスリン分泌不全によりグルコースの排泄量が増加し尿量が増えます。高カルシウム血症でもカルシウムの排泄増加で頻尿を来たします。
副腎皮質ホルモンや抗利尿ホルモンの分泌異常も頻尿の原因となります。これらホルモンは体液調節に深く関与しているため、分泌異常は頻尿を引き起こします。
心不全では全身の浮腫みにより体液量が増加し尿量が増加します。心機能の低下で身体に水分が滞留することが頻尿の原因となっています。
2. 発見方法と対策
頻尿は排尿パターンの変化なので、日頃の観察が大切です。定時の排尿回数や1回量を記録し、異常を早期に捉えることが重要です。
対策は原因疾患の治療が基本です。膀胱炎では抗生物質、腎不全では食事療法、尿路結石では除去手術など、個々の病態に合わせた治療が必要です。
高齢犬の頻尿には制限食の導入や適度な運動が頻尿を抑えるのに有効な場合もあります。
頻尿の原因追究には血液検査や画像検査が欠かせません。獣医師の診断により病態を把握し、個々に適した治療法を選択する必要があります。
3. 考えられる病気
- 糖尿病
- 子宮蓄膿症
- 尿崩症
- 腎不全
- 糸球体腎炎
- クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
- アジソン病(副腎皮質機能低下症)
- 免疫介在性溶血性貧血(IMHA)
泌尿器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬のおしっこの量が減る原因には、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つは、犬自身の体調や状態の変化に関係するものです。
例えば、高齢の犬ほどおしっこの量が減る症状が出やすい傾向にあります。これは、加齢に伴って腎臓の働きが低下することが関係していると考えられています。
また、プードルやシーズーなどの長身種の犬は、体格的に腎臓への血流が不足しやすく、おしっこの量が減りやすいのが特徴です。
そのほか、体調不良時やストレスなどで通常よりも水分摂取量が減ってしまった場合も、おしっこの量は減ることがあります。
もう1つのパターンは、腎臓疾患や膀胱疾患、尿路結石などの病気が原因でおしっこの量が減るケースです。
腎不全は腎臓の機能障害で、老化や慢性的な腎臓病などによって腎臓の働きが低下した状態を指します。腎不全が進行すると、体内の老廃物が排出できなくなり、おしっこの量が減少します。
膀胱炎は膀胱の炎症で、細菌感染などを原因とします。膀胱炎があると膀胱の収縮力が弱まり、おしっこの量が減ることがあります。
尿路結石は、結石が尿の通り道をふさぎ、おしっこの量が減る原因となります。
このように、おしっこの量の減少には犬の体調や加齢、病気など、様々な要因が関係しています。
中でも要注意なのは、おしっこの量が「急激に」減少したケースです。
おしっこの量が通常の半分以下に激減したり、ほとんどおしっこができなくなった場合は、腎臓疾患や膀胱疾患などの病気が原因である可能性が高く、緊急事態を示していると考えられます。
2. 発見方法と対策
まず大切なのは、普段のおしっこの回数と量を把握しておくことです。
1日のおしっこの回数と、1回あたりのおしっこの量を観察し、これまでの状態と比較することで、減っているかどうかを判断できます。
おしっこの色や臭いにも異変がないか、確認するようにしましょう。
その他、おしっこが全くできない、血尿が混じるなどの異常がないかもチェックが必要です。
これらの観察からおしっこの量の減少が確認された場合は、速やかに獣医師の診察を受けることをおすすめします。
特に量の減少が急激だったり、他の症状も見られる場合は、腎臓疾患や膀胱疾患などの可能性があるため、早期の受診が重要です。
高齢の犬では、半年に1回程度の定期検診を行うことで、病気の早期発見につながります。
獣医師による診察の結果、病気が見つかった場合は、投薬や食事療法、場合によっては手術などの治療を行います。
一方、特に病気が見つからない場合は、飲水量を増やすなどの対処が可能です。
以上のように、犬のおしっこの量の減少は様々な要因が考えられます。
観察で減少に早めに気付き、必要に応じて獣医師の診察を受けることが大切です。状況に応じて、適切な対策を行っていきましょう。
3. 考えられる病気
- 前立腺腫瘍
- 前立腺肥大
- 腎不全
- 糸球体腎炎
- 尿道結石
- 膀胱結石
- 膀胱炎
- 会陰ヘルニア
泌尿器の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
四肢(手足)・関節の症状
1. 原因と傾向
犬の歩き方がおかしくなる原因はさまざまですが、代表的なのが関節疾患、脊椎疾患、神経疾患です。
関節疾患では、関節の変形や関節内面の軟骨が磨り減ったり浮き上がったりする変性変化、関節液の減少や炎症が起こることで、歩行時の痛みや可動域の制限から歩行障害が生じます。主な関節疾患としては、先天性の股関節形成不全、加齢に伴う変形性関節症、外傷後の関節の不全などがあります。
脊椎疾患では、椎間板の変性による椎間板ヘルニア、椎骨への外傷、脊柱の炎症を伴う脊椎炎などで、圧迫された神経から痛みが生じたり、麻痺などの神経障害が起こることで、歩行時の痛みや脚力の低下から歩行困難となります。
神経疾患では、外傷や腫瘍などによって脊髄や末梢神経が障害されることで、神経を通じた歩行運動の伝達や制御に支障が出て、歩容の異常を引き起こします。認知症でも歩行障害がみられることがあります。
このように、歩き方の異常の原因には、関節、脊椎、神経などに起因するいくつかのパターンがあるため、他の症状と合わせて総合的に判断する必要があります。
2. 発見方法と対策
歩き方の異常が見られた場合、まずは歩行時の痛がりや不自然な動きがある部位を確認します。例えば後肢の関節に原因があるのか、腰部の痛みが関係しているのかを観察します。
次に、他の症状の有無をチェックし、食欲や活動性の変化、体重の増減も観察します。
症状に応じてレントゲン検査やMRI、CTなどの画像検査を行い、変形の有無や神経の圧迫などを確認し、原因の特定を試みます。
原因が特定できれば、関節疾患なら鎮痛剤の投与やリハビリ、脊椎疾患なら固定具の装着、神経疾患なら手術などの適切な治療を開始できます。
以上のように、歩き方の異常の特徴を確認し、他の症状と合わせて原因を推定し、検査結果に基づき個別の治療を行うことが大切です。異変に早めに気づいて受診することをおすすめします。
3. 考えられる病気
- 認知症(痴呆/認知機能障害/認知障害症候群)
- 骨折
- 股関節形成不全(股関節形成異常)
- 変形性骨関節症(DJD)
- 椎間板ヘルニア
- クリプトコッカス症
- 脳腫瘍
- 水頭症
- 白内障
- 内耳炎
- 肺動脈狭窄症
- 門脈シャント
四肢(手足)・関節の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬が足を痛がる原因としては、関節疾患、外傷・骨折、腫瘍などが代表的です。
関節疾患では、変形性関節症による軟骨の変性と関節腔の狭小化、リウマチなどによる関節炎が主な原因となり、歩行時の疼痛を引き起こします。変形性関節症は加齢に伴う変性的な疾患ですが、肥満などによる関節への負担も発症の要因となります。関節リウマチは自己免疫疾患による炎症性疾患で、四肢の末梢関節に対称性の腫脹と疼痛を特徴とします。
外傷・骨折では、自動車事故や高所からの落下、ケンカなどによる関節の捻挫や骨の骨折が起因となり、強い痛みを発生させます。特に脊椎を含む骨盤周辺の骨折は、神経を圧迫することで激しい痛みを訴えます。
腫瘍では、骨肉腫などの骨に発生する悪性腫瘍によって激しい疼痛が生じます。腫瘍の増大と浸潤により骨が破壊されることで持続的な痛みが発生します。
このように、足を痛がる原因には大別して関節、外傷、腫瘍といったパターンがあり、症状や部位から原因を推測する必要があります。
2. 発見方法と対策
まず痛がる足の部位と症状の程度、性状を詳細に確認します。関節疾患では起床時の痛みが特徴的です。
次に、腫れや発赤、歩容の異常、熱感の有無を確認します。
レントゲンやMRI、CTなどの画像検査、血液検査を行い、骨や関節の状態を調べ、外傷、腫瘍、関節疾患の有無を確定させます。
原因が特定できれば、関節疾患なら鎮痛剤投与と運動療法、外傷なら固定とリハビリ、腫瘍なら抗癌剤や放射線治療など、個別の症例に応じた適切な治療を開始することができます。
以上のように、症状の特徴を踏まえ、検査結果に基づき原因を特定し、個別の治療を行うことが大切です。
3. 考えられる病気
- 認知症(痴呆/認知機能障害/認知障害症候群)
- 関節リウマチ(リウマチ様関節炎)
- 骨折
- 股関節形成不全(股関節形成異常)
- 変形性骨関節症(DJD)
- 椎間板ヘルニア
- 前十字靭帯断裂
- 膝蓋骨脱臼
- レッグ・ペルテス病(レッグ・パーセス病)
- 骨肉腫
四肢(手足)・関節の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の座り方がおかしくなる代表的な原因は、腰痛や後肢の筋力低下、関節痛などです。
腰痛の場合、椎間板ヘルニア、脊椎炎、脊柱腫瘍などで腰部に強い痛みが生じ、正しい座り姿勢が取れなくなったり、痛がるためにずれた姿勢で座ったりすることがあります。特に椎間板ヘルニアでは、椎間板内のゲル様内容物が脊髄を圧迫することで激しい痛みが生じます。
後肢の筋力低下では、加齢に伴う筋萎縮や神経障害で後肢の筋力が衰え、適切に体重を支えられなくなるため、座った時に後肢が不安定になったり、尻餅をついたりすることがあります。
関節痛の場合は、変形性関節症やリウマチで関節に慢性的な痛みがあるため、痛みを避けるように姿勢を変えて座ったり、片方の脚を上げて座ったりする姿勢が多くなります。
このように、座り方の異常は腰痛や後肢の機能低下が複合的に関係することが多く、原因の特定が難しいケースも少なくありません。
2. 発見方法と対策
まず座る時の様子を詳しく観察し、痛がるタイミングや部位、不安定な動きがないかを確認します。
他の症状の有無も確認する必要があります。例えば歩行時の異常や排泄時の痛みなど、関連する症状がないかをチェックします。
レントゲンやMRI、CTなどの画像検査で、腰椎や関節の状態を確認し、腰痛や関節痛の原因を特定して治療方針を立てます。
原因に応じて、鎮痛剤の投与、温熱療法、運動療法、マッサージなどを行い、個別の症例に合わせて症状の改善を図ります。
以上のように、座り方の変化の特徴を確認し、他の症状と合わせて原因を推定し、個別の治療を行うことが大切です。
3. 考えられる病気
- 関節リウマチ(リウマチ様関節炎)
- 骨折
- 股関節形成不全(股関節形成異常)
- 変形性骨関節症(DJD)
- 椎間板ヘルニア
- 前十字靭帯断裂
- 膝蓋骨脱臼
- レッグ・ペルテス病(レッグ・パーセス病)
- 骨肉腫
四肢(手足)・関節の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
1. 原因と傾向
犬の関節が腫れる主な原因は、関節リウマチや変形性関節症などの関節疾患です。
関節リウマチは若齢から中年齢の小型犬に多く、自己免疫反応による慢性関節炎です。特に四肢の指趾関節に対称性の腫脹と硬直を引き起こします。病初期から放置すると変形性関節症へと移行する可能性が高い疾患です。
変形性関節症は加齢に伴う代表的な関節疾患で、関節軟骨の変性と骨棘形成により関節隙が狭まり、腫れと可動域制限をもたらします。大型犬ほど早期に発症する傾向にあります。
関節脱臼や靱帯断裂などの外傷後も、変性性の変化が加わり慢性的な関節腫脹を生じます。
また、リンパ腫や転移性腫瘍などでも、関節内や周囲の組織の腫大により関節腫脹が見られることがあります。
このように、関節腫脹の原因には多岐にわたる疾患が関係しており、症状や検査結果から総合的に判断する必要があります。
2. 発見方法と対策
関節の腫れが見られた場合、まず部位と対称性、発症の急激さを確認します。リウマチ性疾患では対称性が特徴です。
次に、疼痛の程度や性状をチェックします。変形性関節症では動作痛が典型的です。
血液検査や画像検査により、原因となる変性や炎症の程度を評価します。
原因に応じて、NSAIDsによる痛み・炎症の抑制、食事・運動療法による体重調整、手術による形態の修復など、個別の治療法を設定します。
早期発見と適切な治療で、変形の進行を最小限に抑えることが大切です。関節に異常を感じたら受診をおすすめします。
3. 考えられる病気
- 関節リウマチ(リウマチ様関節炎)
- 変形性骨関節症(DJD)
四肢(手足)・関節の症状がある場合、これらの疾患等が考えられますが、獣医師による診断が必要不可欠です。 治療方針は病気の原因と状態によって異なります。
本ページには細心の注意を払ってコンテンツを掲載していますが、その正確性、安全性、有用性等について、お客さまに対し、何ら保証するものではありません。コンテンツのご利用により、直接または間接であるかを問わず、万が一何らかの問題、損害・損失が発生した場合でも、弊社は一切の責任を負いかねます。コンテンツのご閲覧・ご利用等にあたっては、お客さまご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。